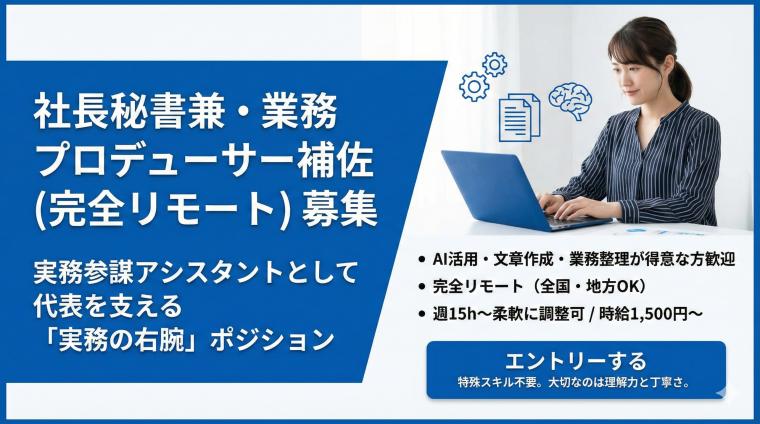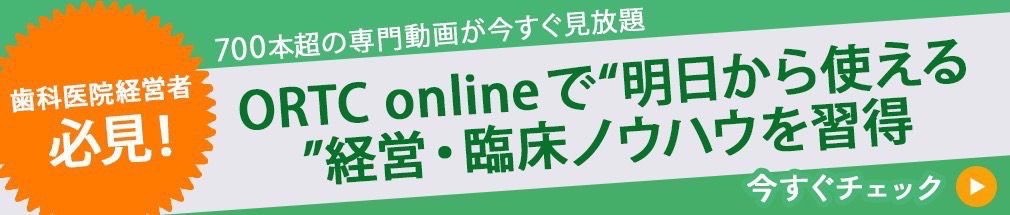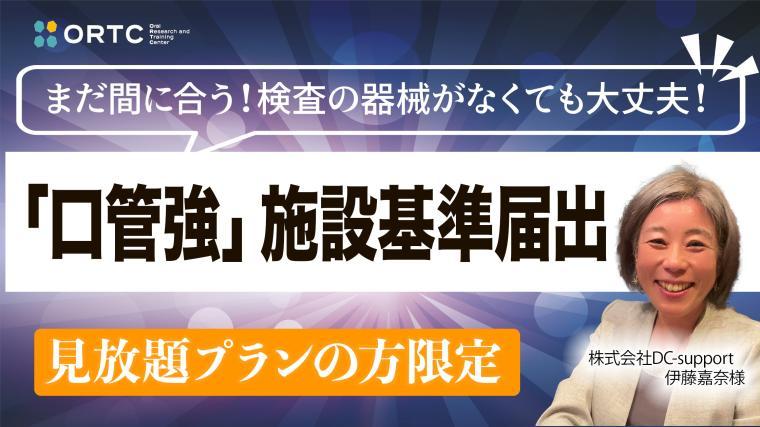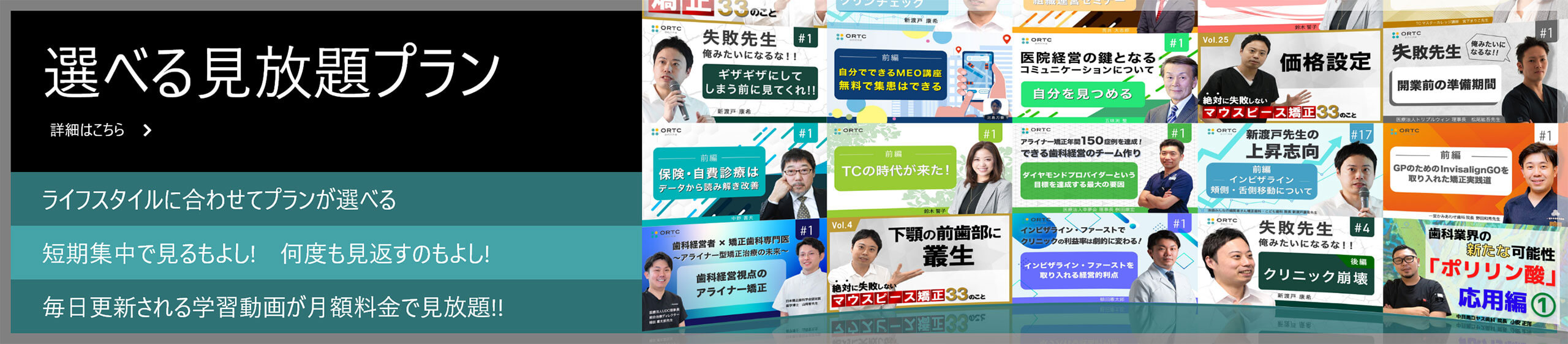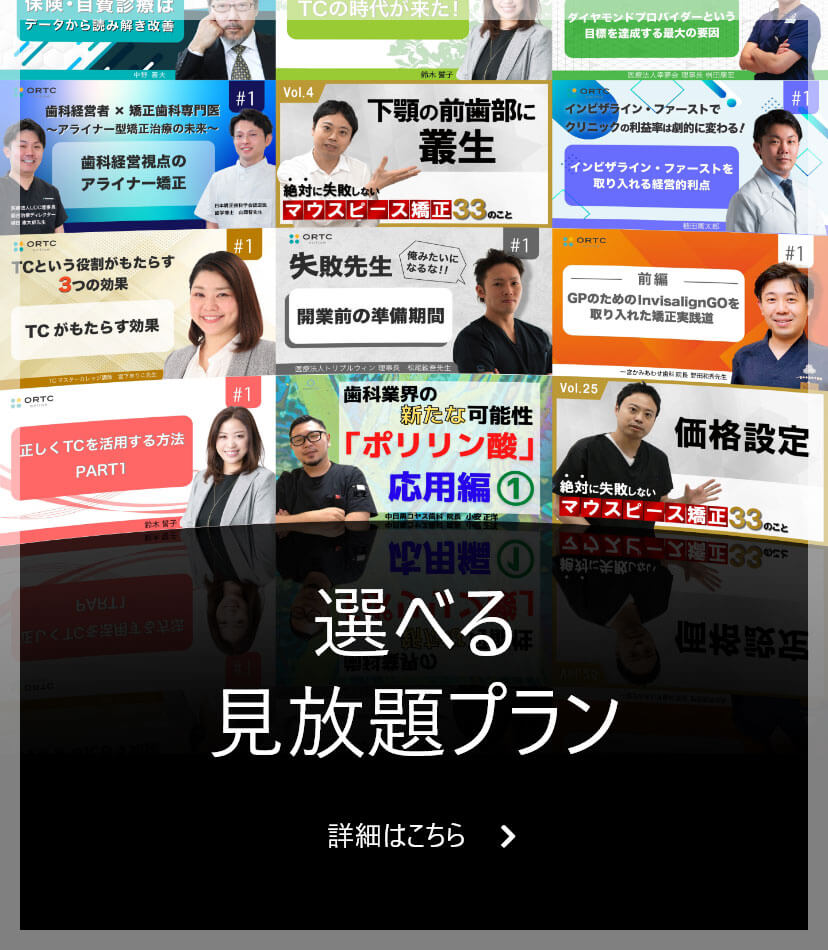※本稿は、2025年3月4日に逝去された
医療法人社団プレシャスワン前理事長・三木尚子先生のご功績を偲び、
生前にORTCで共有された知見を後世に伝える目的でまとめた追悼記事です。
記事内の講演・活動はすべて “生前の記録” に基づいています。
予防歯科の重要性が高まるなか、その最前線に立ってこられたのが、医療法人社団プレシャスワン理事長 故・三木尚子先生 でした。 生前のORTC オンライン講演では、最新の予防医療理論を豊富な臨床例と共に紹介され、患者教育と医療の質的向上を両立させる手法を示してくださいました。
臨床と教育の両立は歯科界の難題ですが、三木先生は 実践知の共有 という形で橋渡し役を担われました。 専門医としての豊富な症例に裏打ちされた理論展開は、若手からベテランまで多くの歯科医師に刺激と指針を与えています。
三木尚子先生×ORTC講演の意義

歯科界において、臨床と教育の両立は難題とされがちです。しかし、三木尚子先生の講演は、両者を橋渡しする実践知の共有という点で意義深いものでした。専門医としての臨床経験に基づいた理論展開と、日々の診療現場での応用例が融合した本講演は、若手歯科医師にとっての指針であり、経験豊かな臨床家にとっても再考の契機となります。
生前のSNS発信と予防歯科啓発

現代の患者との接点は、診療室の外にも広がっています。生前・三木尚子先生は、SNSを活用した予防歯科の啓発に積極的に取り組み、専門知識を親しみやすく発信されました。お名前も、尚子先生(なおこ先生)の呼称で視聴者に非常に親しまれていました。その姿勢は、患者の自律的な行動変容を促す“教育型医療”の一例として今もなお注目されています。
YouTube・TikTokを通じた啓発活動
動画コンテンツは、単なる宣伝ではなく、口腔内トラブルへの知識と対策を学べる教育ツールとして設計されています。たとえば、虫歯予防のポイントや歯磨き指導など、視聴者の関心を引きつけながら、科学的な根拠に基づく情報を提供していました。特に若年層への影響力は大きく、啓発の新しい形として定着しつつあります。
DMFTシミュレータで変わる定期通院率と患者の行動変容
三木先生のクリニックでは、患者自身が視覚的に将来のう蝕リスクを理解できる「DMFTシミュレータ」を導入しています。これにより、通院動機の形成や予防意識の定着が進み、実際に定期通院率が向上し、デジタルツールを通じた「見える化」が、予防行動の第一歩となっています。
H3:「CAPシステム」による歯質強化と予防医療の融合
CAPシステムは、う蝕予防の科学に基づき、再石灰化を促すメカニズムに重点を置いた予防手法です。三木先生はこれを患者指導と連動させ、フッ素応用・栄養管理・リスク評価など多角的なアプローチを展開しました。予防医療と歯科治療が融合する、次世代型の歯科医療モデルを提示していました。
4本柱で見る診療哲学|教育・予防・強化・ミニマル治療
「教育」「予防」「歯質強化」「ミニマル治療」。三木先生の診療理念は、この4本柱で構成されました。過剰治療を避け、できるだけ“削らない・抜かない”を重視する治療スタンスは、患者にとっても安心感のある診療方針でした。
三木尚子先生の駿河台・デンタルオフィスの挑戦(生前の実践例)

患者本位の「通いたくなる歯科医院」を実現しています。
CAPシステムの診療導入例と患者満足度向上
三木尚子先生が生前に導入した CAPシステムにより、患者のリスク評価からアプローチ方法までが明確化され、個別対応が可能となりました。その結果、患者満足度が高まり、口コミや紹介による来院も増加しています。
神保町で実現する地域密着モデル
三木尚子先生が生前に重視された地域との信頼関係構築を受け継ぎ、同クリニックでは地元住民やオフィスワーカーへの啓発活動が引き続き行われています。通いやすさと安心感を両立した地域密着型歯科医院のモデルケースとして注目されています。
「奇跡の歯ブラシ」とは何か?患者指導とオーラルケア啓発の象徴
「奇跡の歯ブラシ」は、株式会社西尾が開発し、三木尚子先生がイメージキャラクターを務めていた歯ブラシです。毛先がピラミッド形状で斜めに尖っているのが特徴です。そのため、従来通り適当に磨くだけでも、歯と歯の間の汚れがしっかりと落ちます。
SNS・オーラルケアブランドと歯科ブランディング
三木先生は、自身の診療理念に基づくオーラルケアブランドを立ち上げ、SNSと連携させた情報発信を展開し、商業的要素に偏らず、患者啓発と歯科のブランディングを行っていました。
精度と効率を両立するデジタル矯正の戦略|三木尚子先生が携わったSmile TRU

三木尚子先生は生前に、矯正治療の合理化と精密性向上の両立を目指し、米国発のマウスピース矯正「Smile TRU」の日本展開に深く関与してきました。このシステムは、従来の矯正装置と異なり、透明で目立ちにくく、患者の生活への負担が少ないことが特長です。また、歯科医師の診断・設計に基づいた段階的な治療プランにより、無理なく効果的な治療を進めることが可能となります。
Smile TRUとその他のマウスピース矯正(インビザライン、シュアスマイルなど)違いについて
Smile TRUは、患者ごとにカスタマイズされたアライナーを、段階的かつ現実的な動きで設計する点において、他のシステムと一線を画します。特に、治療計画の自由度と技工工程の透明性に優れており、国内ラボとの連携も可能なため、即応性と品質の両立が図られています。他の代表的なブランドと比較しても、コストや柔軟性、指示のしやすさといった点で臨床的利点が認められています。
アライナー矯正の診断・治療計画で得られる臨床的成果
三木先生は、矯正診断の初期段階での精密な分析と、シミュレーションソフトによる予後予測を重視していました。これにより、患者との信頼構築が進み、治療の継続率や満足度も向上。特に、軽度~中等度の症例において、従来のワイヤー矯正に比べて高い受容性と整合性を確保できるようになりました
症例を通じて学ぶ|成功の鍵と課題の共有
三木先生は生前に、数多くの症例データを基に、アライナー矯正の成功には「適切なケース選定」と「精緻な初期診断」が不可欠であると述べています。また、患者のセルフマネジメント能力や、装着時間の遵守など、啓発とモチベーション維持の重要性も指摘。医療者と患者の“協働”によって結果が左右される治療分野であることを実感させられます。
デジタル矯正|学びとメリット

デジタル矯正は、歯科医師・歯科技工士・歯科衛生士・学生それぞれに異なる学びとメリットを提供する革新的技術です。三木先生はそれぞれの立場から見た可能性を提示し、歯科界全体のスキル底上げに貢献する知見を共有していました。
矯正歯科医が得られる「治療計画の最適化」と「精度向上」
従来の模型・印象材に依存しないデジタル設計は、診断の精度と治療結果の再現性を大幅に高めます。また、クラウドを活用したデータ共有により、複数の専門家との連携も円滑に進みます。
一般歯科医が得られる「連携」と「治療範囲の拡張」
一般歯科医師がアライナー矯正を導入することで、患者のニーズに応える幅が広がり、他院との連携体制も強化されます。特にSmile TRUは、導入しやすい教育体制とサポートが整っている点が評価されています。
歯科技工士への示唆|内製ラボとデジタル対応力の育成
歯科技工士にとって、CAD/CAMや3Dプリンターとの連動は今や必須スキルです。三木先生は、自院内でのラボ育成にも注力しており、外部依存から脱却する「内製技工」の有効性を提唱しています。
歯科衛生士に求められる“定期管理スキル”の進化
アライナー矯正の定期観察では、歯科衛生士が担う役割も大きくなります。装着状況の確認や口腔衛生管理の指導はもちろん、患者の意識変容を促す「対話力」がより重視されるようになっています。
歯科学生・若手歯科医師が未来を考えるヒント
新たな矯正技術の導入は、キャリア初期の歯科医師にとって大きな強みになります。三木先生は「今こそ多様な症例に触れ、実践と理論の両面を磨く好機」と述べ、若手世代への積極的なチャレンジを後押ししています。
今こそ考える、矯正臨床の未来

矯正歯科は、単なる歯並びの調整にとどまらず、審美性や機能性の回復、そしてQOL(生活の質)向上に貢献する医療です。近年では、デジタル技術の急速な進展により、診断・治療・管理のすべてが大きく変化しつつあります。今後は、より多くの歯科医師が矯正臨床に参入することが予想され、専門家同士の役割分担や協働体制が一層求められるでしょう。
デジタル技術がもたらす新たなスタンダード
AIを活用した診断支援、3Dプリンティングによるアライナーの迅速な製造、遠隔モニタリングなど、新たな技術が矯正の在り方を根本から変えつつあります。これまでのような「経験と勘」に依存する時代から、客観性と再現性を重視した治療へと移行しており、これが新しいスタンダードとなっていくでしょう。
三木尚子先生が講演されたセミナー情報

「CAPシステム×予防歯科 実践ウェビナー」
講師(録画講演): 故・三木尚子 先生(医療法人社団プレシャスワン 前理事長):
形式: 動画(見放題/レンタル/有料)
視聴料金: ¥1,980(税込)
https://ortc.jp/movie/osusume/fluorine
概要:
- CAPシステムとDMFTシミュレータの基本と臨床応用
- フッ素応用をベースにした、予防歯科の新たな診療モデル
- 現代患者ニーズに応える「安全性×予防」の診療提案
- 歯科医院が抱える構造的課題への具体的な解決策
こんな方におすすめ:
- 予防歯科に注力している/シフトしたい歯科医師
- 自費診療の質を高めたい医院経営者
- 患者満足度を高めたい院内チーム
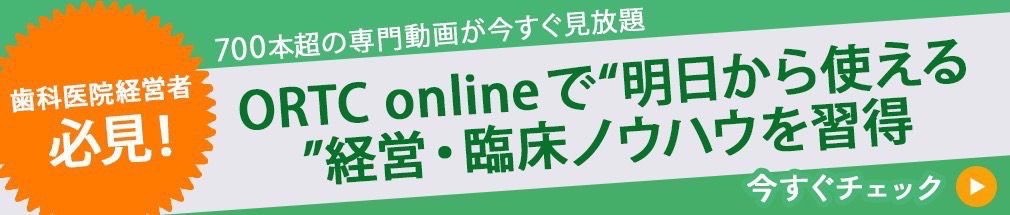
Q&A
Q1. 三木尚子先生の専門領域や経歴について教えてください。
A.
三木尚子先生は、日本矯正歯科学会認定の専門医・指導医であり、東京・神保町にある「駿河台・デンタルオフィス」の院長として、矯正歯科と予防歯科を融合させた診療に取り組まれました。
デジタル矯正の先駆者として、iTeroやインビザラインを活用した先進的な臨床を展開。SNSや講演活動を通じて、歯科医療の普及にも積極的に貢献されました。
Q2. CAPシステムとは何ですか?三木尚子先生が関わっていた理由は?
A.
CAPシステムは、歯質の強化と最小限の介入治療を両立する予防的な診療モデルで、三木尚子先生が臨床現場で体系化したアプローチです。「教育・メンテナンス・歯質強化・ミニマル治療」の4本柱を軸に、歯科衛生士や患者との連携を重視しながら、患者の口腔健康の長期維持を目指します。
Q3. 「奇跡の歯ブラシ」とは何ですか?本当に効果があるのでしょうか?
A.
「奇跡の歯ブラシ」は、三木尚子先生が推奨された歯ブラシの一つで、毛先がピラミッド形状で斜めに尖っているのが特徴です。この特殊な形状により、患者のブラッシング精度を自然に高めるための設計が特徴です。先生の診療方針である「定期管理・患者教育」と連動した使用指導により、実際に患者のプラークコントロール率が向上した例が多く報告されています。
Q4. 三木尚子先生はSNSで情報発信していましたか?
A.
三木尚子先生はtiktokやYouTubeを活用し、口腔ケアや矯正歯科に関する教育的コンテンツを積極的に発信されていました。
とくに若年層の患者へのアプローチや、保護者向けの予防教育にも力を入れており、SNSを通じた啓発が、実際の診療所来院にもつながっている事例が増えています。
Q5. なぜORTCでの講演が注目されているのでしょうか?
A.
ORTCは、実践的かつ臨床重視の学術団体として歯科医師の支持を集めており、そこでの登壇は専門性と信頼性の証とされています。三木尚子先生の講演は、症例に基づくリアルな実践知と、SNS発信やデジタル技術を絡めた先進性が両立している点が特徴で、矯正・予防・経営の各視点で多くの学びが得られる内容となっています。
まとめ
三木尚子先生は、予防歯科とデジタル矯正の融合を先導する実践家でした。ORTC講演では、CAPシステムやDMFTシミュレータ「奇跡の歯ブラシ」など独自のアプローチを紹介されました。SNSを通じた啓発やSmile TRUによる矯正の工夫を通じて、患者本位の歯科医療の未来像を提示されました。
本記事を通じて三木尚子先生のご功績が今後も語り継がれますよう、心よりご冥福をお祈り申し上げます。
歯科衛生士ライター:西
【参考URL】
https://clean-teeth.net/protection/#section4
歯科医療の現場で役立つ実践的な知識を届けるORTC

ORTCは「笑顔の役に立つ」を理念に、歯科界の知識を共有する場を目指しています。歯科医療の現場で役立つ最新の知識と技術を提供することで、臨床と経営の両面からクリニックの成長を支援します。最先端の技術解説や経営戦略に特化した情報を集約し、歯科医療の現場での成果を最大化。自己成長を追求するためのコンテンツをぜひご活用ください。
無料会員登録
無料動画の視聴、有料動画のレンタルが可能です。歯科業界についてのオンライン・オフラインセミナーへの参加が可能となります。
ORTCPRIME
月額5500円で、 ORTC内のすべての動画を見放題に。臨床の現場に役立つ最新の技術解説や、歯科医院経営の成功戦略を網羅した特別コンテンツをご利用いただけます。 歯科業界の方へ効率的に知識を深めていただける内容です。
ORTC動画一覧
ORTCセミナー一覧
まずは無料会員登録
こちらのリンクより会員登録ページへお進みください。
会員登録はこちら
ORTCPRIMEへのアップグレードも簡単!
登録後は「マイページ」から、ORTCPRIMEにいつでもアップグレード可能です。
 こちらの動画もおすすめです
こちらの動画もおすすめです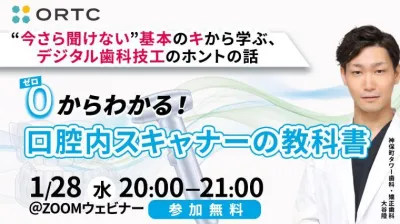 “今さら聞けない”基本のキから学ぶ、デジタル歯科技工のホントの話『ゼロからわかる、口腔内スキャナーの教科書』
“今さら聞けない”基本のキから学ぶ、デジタル歯科技工のホントの話『ゼロからわかる、口腔内スキャナーの教科書』 歯科医師のキャリア戦略 ― 勤務医・開業・M&A・資産形成まで、後悔しない選択とは ―
歯科医師のキャリア戦略 ― 勤務医・開業・M&A・資産形成まで、後悔しない選択とは ―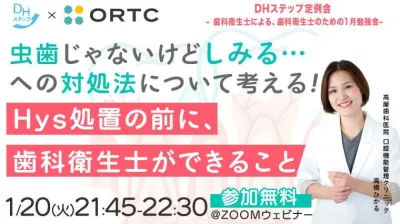 虫歯じゃないけどしみる…への対処法について考える Hys処置の前に、歯科衛生士ができること
虫歯じゃないけどしみる…への対処法について考える Hys処置の前に、歯科衛生士ができること 「TBIが変われば患者が変わる」 自費TBI成功マインド
「TBIが変われば患者が変わる」 自費TBI成功マインド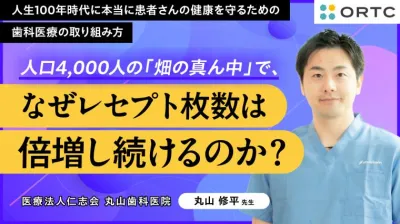 人口4,000人の「畑の真ん中」で、なぜレセプト枚数は倍増し続けるのか?
人口4,000人の「畑の真ん中」で、なぜレセプト枚数は倍増し続けるのか?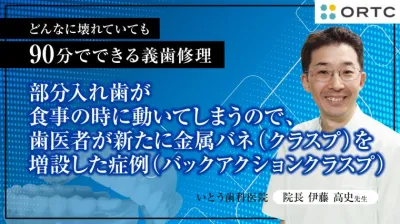 部分入れ歯が食事の時に動いてしまうので、歯医者が新たに金属バネ(クラスプ)を増設した症例(バックアクションクラスプ)
部分入れ歯が食事の時に動いてしまうので、歯医者が新たに金属バネ(クラスプ)を増設した症例(バックアクションクラスプ)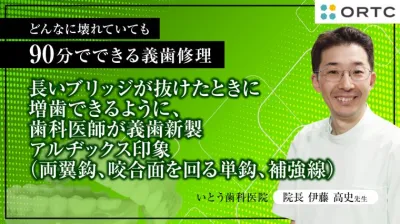 長いブリッジが抜けたときに増歯できるように、歯科医師が義歯新製 アルヂックス印象(両翼鈎、咬合面を回る単鈎、補強線)
長いブリッジが抜けたときに増歯できるように、歯科医師が義歯新製 アルヂックス印象(両翼鈎、咬合面を回る単鈎、補強線)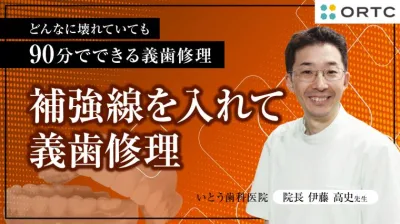 補強線を入れて義歯修理
補強線を入れて義歯修理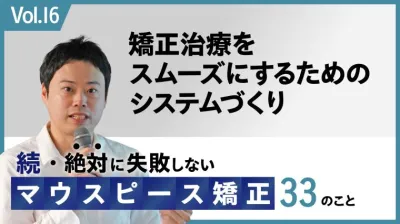 続・ 絶対に失敗しないMP矯正33の事 システムづくり
続・ 絶対に失敗しないMP矯正33の事 システムづくり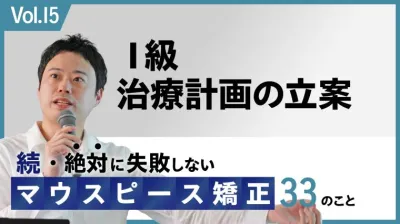 続・ 絶対に失敗しないMP矯正33の事 Ⅰ級 治療計画の立案
続・ 絶対に失敗しないMP矯正33の事 Ⅰ級 治療計画の立案