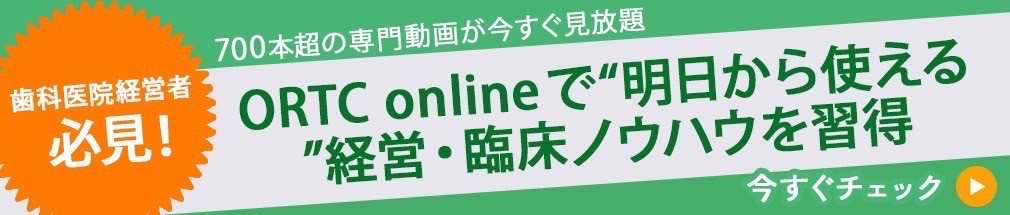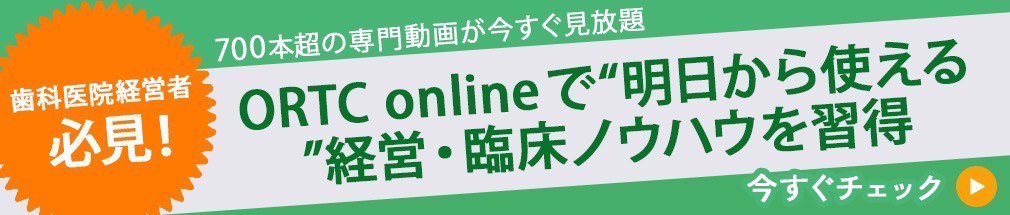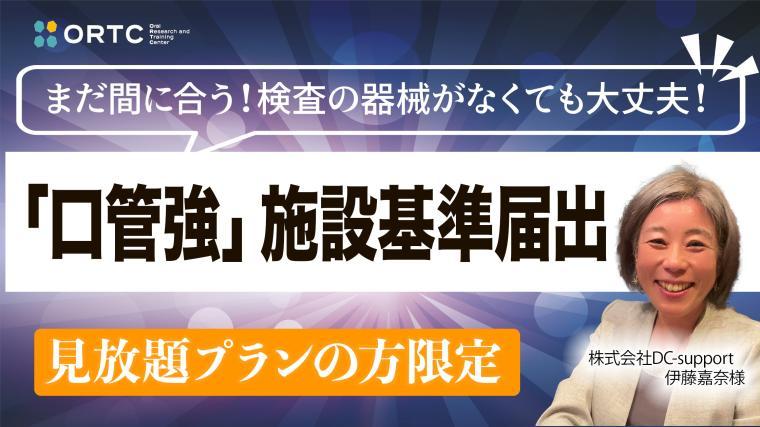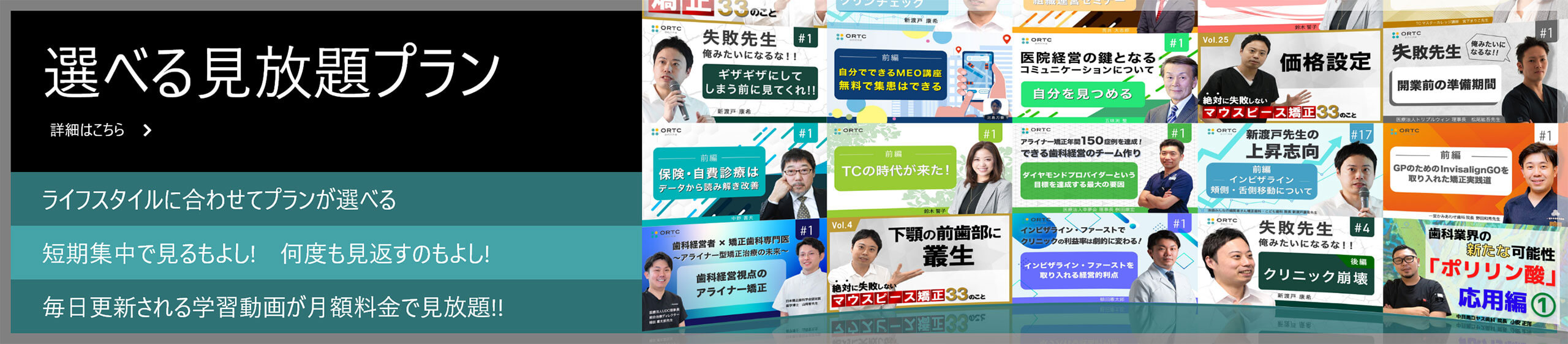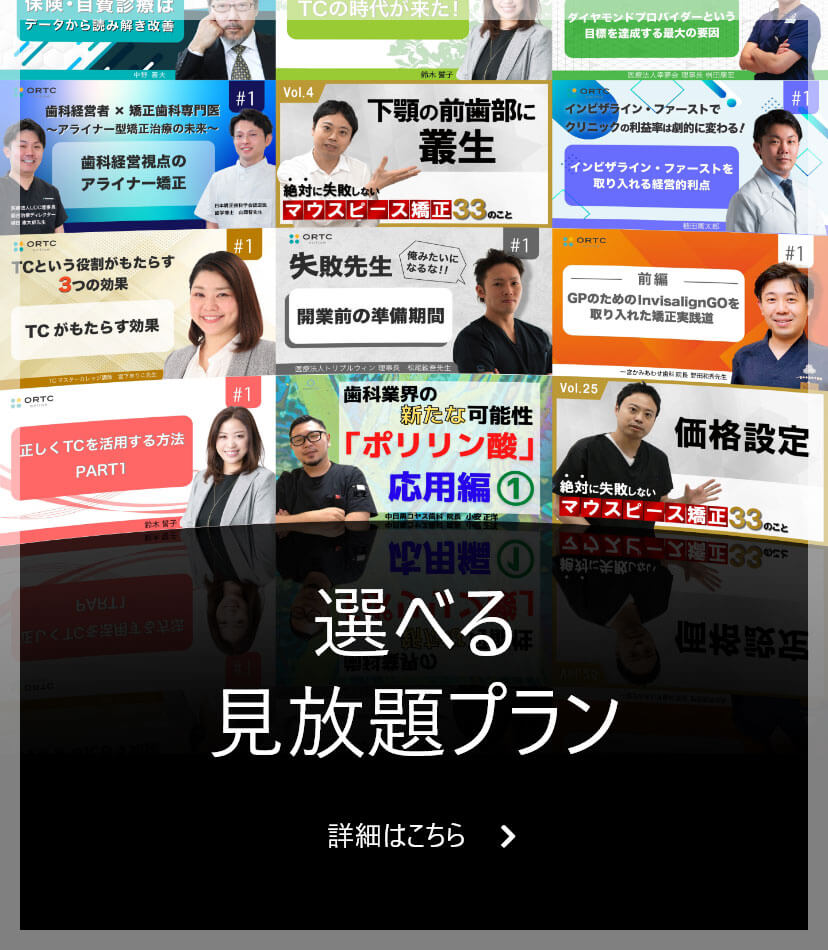「先生、なんか入りづらい気がします…」「アライナー、ちょっと浮いてるんですが…」
そんな患者の一言に、ドキッとした経験はありませんか?
事前の対応で防げた可能性があるトラブルかもしれません。
マウスピース矯正は“装着するだけ”の簡単な治療に見えますが、装置の破損・紛失・浮き・装着不足・アタッチメントの脱離など、トラブルが多発しやすい治療法でもあります。
見た目のスマートさとは裏腹に、治療計画・装着指導・モチベーション管理において、高い専門性と患者との密な連携が求められます。
「なぜアライナーが浮くのか原因が特定できない」「トラブルが起きたときの対応をスタッフ全体で共有できていない」そんな課題を抱えている歯科医師や歯科衛生士の皆さんへ。
本記事では、マウスピース矯正中に起こりやすいトラブルの要因、症例別の対応法、職種別の予防ポイントを解説していきます。
患者満足度と治療精度を両立させる院内対応のスタンダードを知り、患者様に「やらなきゃよかった」「思ってたのと違った」と後悔させないために現場で役立つトラブル対策の知識とスキルを今、アップデートしましょう。
なぜマウスピース矯正でトラブルが起こるのか?

マウスピース矯正のトラブルは、明らかな原因があり発生しています。
マウスピース矯正で起こる多くのトラブルは、患者要因、歯科医院要因、生物学的要因の3つに大きく分けられます。
いつ・誰が・どう対応するかをあらかじめ整理しておくだけでも、トラブルの予防や早期発見につながります。
マウスピース矯正でよくある「原因のパターン」を3つの視点からみていきましょう。
患者要因|装着時間不足・チューイー未使用・自己判断で中断
マウスピース矯正で頻発するのが、患者自身による装着時間の不足や自己管理の甘さによるトラブルです。
マウスピース矯正では「1日20時間以上のアライナー装着」が条件となっています。
実際には「寝るときしかつけていない」「昼間は外したまま」「つけ忘れたまま外出していた」など、アライナーの装着時間の確保が不十分なケースも多いことでしょう。
実際に勤務している歯科医院でも「チューイーは使わないといけませんでしたか?」と患者様の認識がズレている場合も多いです。
正しい使用方法が習慣化されないまま治療が進行すると、アライナーの浮きや歯の動きの遅れといった問題が生じ、治療計画にズレが生じるリスクが高まります。
このようなトラブルは、治療前の丁寧な装着指導、定期的なチェック、患者との信頼関係によって、ある程度は未然に防ぐことが可能です。
こうしたリスクを防ぐには、初期指導時に装着の重要性だけでなく「守らなかった場合にどうなるか」というリスクも具体的に伝えることも必要です。
定期チェックでの声かけを通して、アライナー装着習慣とモチベーション維持をサポートする体制づくりが求められます。
歯科医院要因|計画ミス・説明不足・アタッチメントのトラブル
使用状況に問題がないにもかかわらず、治療が計画通りに進まないケースでは、歯科医院側の設計ミスや説明不足が関与している可能性があります。
治療計画の精度、アタッチメントの設置や管理、患者への十分なインフォームドコンセントなど、診療側の体制に起因するトラブルも少なくありません。
アライナーの設計時に、歯の動きに合ったアタッチメントの形状・位置が適切でない場合、必要な箇所にアタッチメントが付与されていない場合など、計画通りに歯が動かない原因になります。
事前に「アタッチメントは取れることがある」「脱離時の対応」について説明がなければ、患者様はアタッチメントが取れたことで「失敗ではないのか」「このままで大丈夫なのか?」と医院への不信感につながる恐れもあります。
マウスピース矯正では、現実的な移動範囲の設定とクリンチェックの綿密な確認が必要です。
説明時には「万が一」に備えた内容も含め、患者様が不安を抱かずに治療に臨める状態をつくることが、歯科医院側の責任といえるでしょう。
生物学的要因|歯の動き方・代謝反応に個人差あり
どんなに治療計画やアライナーの装着管理が適切でも、生体反応の個人差がトラブルにつながることがあります。
同じ治療計画でも「歯が動きやすい人」と「歯が動きにくい人や動かない人」がいるように、骨代謝のスピードや歯の萌出位置などによって、予測通りに歯が動かないケースは少なくありません。
歯が動かない理由がはっきりしないままマウスピース治療を継続してしまうと「マウスピース矯正ができない歯並びだったのでは?」という誤解につながり、患者様との信頼関係にも影響する可能性があります。
歯の動くスピードは個人差があることをあらかじめ説明し、万が一の手段として、追加アライナー・再設計ができることも伝えておきましょう。
治療中も定期的に「想定どおりに進んでいるか?」をモニタリングし、計画とズレがあれば早めに再評価を行うことが、トラブルの拡大を防ぐカギになります。
よくあるマウスピース矯正のトラブルと対処法【症例付き】
 マウスピース矯正のトラブルは、起こってしまったあとも重要になります。
マウスピース矯正のトラブルは、起こってしまったあとも重要になります。
「どの情報をもとに判断するか」「患者様にどう説明するか」で、その後の治療のスムーズさや信頼関係が大きく変わっていくでしょう。
実際の臨床で頻出する代表的なケースを3つ取り上げ、それぞれの判断ポイント・対応フロー・患者様への声かけ例を交えて解説します。
「アライナーがなくなった」「パカパカ浮く」「なんだか動いてない気がする」などの相談を受けたとき、自信を持って対応できる状態をつくるために、ぜひ参考にしてください。
Case① アライナーが破損・紛失した場合の初動対応
患者様から「マウスピースをなくしてしまった」「うっかり破ってしまった」という連絡は、アライナー矯正ではよくあるトラブルの一つです。
患者様から連絡があった際には、紛失・破損したアライナーが何枚目か、どのくらいの期間使用していたかを確認します。装着が数日以内なら、ひとつ前のアライナーに戻す、または新たに再製作するなどの判断が必要です。
「外したまま外食して失くした」「ケースに入れずに破損した」など、日常の取り扱いミスが原因となるケースが多いため、初期指導の徹底と補助アイテム(専用ケース・注意書き)の活用が予防策として有効です。
電話対応の際は、患者様の不安を抑えながら、装着状況と対応の流れを冷静に整理し、必要があれば来院してもらう判断をしていきましょう。
この初動対応の丁寧さが、トラブル時の信頼維持に直結します。
Case② アライナーが浮く・パカパカする
「マウスピースが浮いてる」「前歯の部分がパカパカする」といった訴えは、装着不良や適合不良が疑われる典型例です。
・浮いている部位と程度(前歯部の切端だけ?臼歯部まで?)
・装着時間が20時間以上守られていたか
・チューイーは正しく使用されていたか
患者様に確認をしたうえで、チューイー未使用や装着時間不足が原因の場合は、再指導+一定期間の継続装着で改善するケースが多いです。
それでも改善しない場合は、アライナーの変形や歯の動きの遅れが関係している可能性があり、一つ前のアライナーに戻す対応やアタッチメントの再確認が必要です。
Case③ 動いていない気がする…治療計画の見直しポイント
「マウスピースは入っているけど、違和感が大きい」と患者様から言われたとき、治療の進行が計画通りに進んでいないサインである可能性があります。
定期モニタリングでクリンチェックとのズレが出ていないかを確認しましょう。アタッチメントの脱離、IPRの未実施、装着時間不足なども見直すべき項目です。
進行が遅れている場合には、追加アライナーの検討や、再スキャン→治療計画の再構築が必要になることもあります。
単に再設計するのではなく、「なぜ予定通り進まなかったのか」を患者と共有し、納得のうえで治療を継続することが重要です。
初回の同意書に「再設計や追加アライナーの可能性」も含めておくと、トラブル時の対応もスムーズになり、患者様との信頼関係の維持にもつながります。
このようなトラブルにならないためにも、事前に対策をしていくことが大事です。
ORTCでは、矯正治療について学べる動画も揃えております。
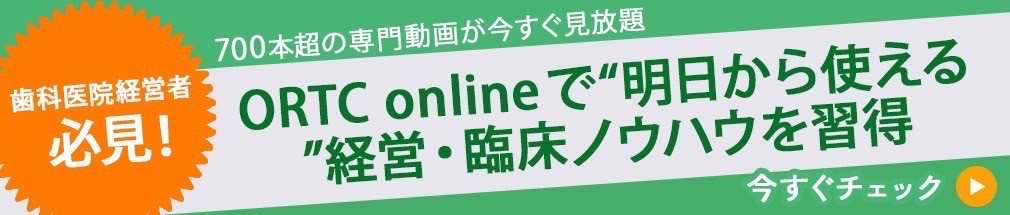
「矯正治療中に起きるトラブルと避けたいトラブル」
講師:Belle歯科・矯正歯科 院長 竹内優斗
マウスピース矯正の失敗を防ぐ予防策
 マウスピース矯正でトラブルを完全にゼロにすることは難しくても、起こりにくくするための仕組みづくりは可能です。
マウスピース矯正でトラブルを完全にゼロにすることは難しくても、起こりにくくするための仕組みづくりは可能です。
治療開始前の説明や、装着方法の指導、そして定期的なフォローアップといった、「予防線」をどこまで張れるかという視点が必要になります。
また、失敗を防ぐためには医院全体での連携も欠かせません。
歯科医師・歯科衛生士・歯科助手がそれぞれの役割を理解し、患者の不安や違和感を早期にキャッチし対応する体制が、治療の成否を左右します。
各職種が現場でできる“明日からの工夫”を具体的にご紹介します。
歯科医師の対応|リスク説明と同意書の徹底
マウスピース矯正では、治療前のリスク説明と同意書の取り扱いが、トラブルを未然に防ぐ重要なカギとなります。アライナーの浮きやアタッチメントの脱離、追加アライナーの可能性など、患者が「聞いていなかった」と感じやすい項目ほど、書面と口頭の両面で丁寧に説明することが信頼構築につながります。
治療計画そのものも、理想に偏りすぎず“現実的に可能な範囲”で設計することが大前提です。
無理のあるクリンチェック設定は、「動かない」「ずれている」といった不満に直結し、医院への不信感を招く要因になります。
同意書には、再設計や再製作の発生時にかかる追加費用や治療期間の延長の可能性なども明記しておきましょう。
予測可能なトラブルとして備えておくことが、歯科医師の責任ある対応姿勢となります。
歯科衛生士の対応|指導・定期確認・モチベ管理
歯科衛生士は、マウスピース矯正において患者指導の最前線に立つ存在です。
初回装着時の指導では、チューイーの正しい使い方や歯磨きのタイミング・方法、痛みが出た場合の対応(市販薬の使用含む)など、患者様が不安に感じやすいポイントを丁寧にカバーすることが重要になってきます。
装着初期は「痛くて眠れない」「外してしまった」などの訴えが出やすく、「ロキソニンなどの鎮痛剤で落ち着くことが多い」などの具体策を添えてフォローすることで、自己判断による中断を防いでいきましょう。
定期来院時には「装着時間は守れているか」「浮いていないか」「不快感がないか」など、コンプライアンスのチェックとフィードバックを忘れずにしていきます。
実際にできているところを褒めて伝える姿勢や経過の進捗状況の共有など、患者様のモチベーションを保っていきましょう。
歯科助手の対応|患者からの小さな声を拾う「初期発見者」役割
歯科助手は直接的な治療行為には関わらないものの、患者と最も近い距離で接する存在として、トラブルの“初期発見者”となることが多々あります。
「最近ずっとケース持ってこない」「今日はアライナー入ってない気がする」といった小さな違和感や「前歯だけ浮くって言ってた」などの何気ない会話が、トラブルの兆候を早期に察知するヒントになります。
大切なのは、それを見過ごさず、すぐに衛生士やドクターに伝える“共有力”です。
その一声があれば、軽微な問題のうちにリカバリーできるケースは少なくありません。
患者からの「痛いけど我慢している」「外したまま寝た」などの相談を受けた際には、自己判断では対応せず、すぐに専門職へ連携する意識を持ちましょう。
チーム医療の中で気づきの感度を高める役割として、助手の存在は非常に重要です。
マウスピース矯正が向かない人とその症例とは?

「マウスピース矯正は誰にでもできる」と思われがちですが、すべての症例に適しているわけではありません。
「動かない」「前歯だけ浮いた」「思ったような結果が出ない」といった声の背景には、適応症の見極めミスが潜んでいることもあります。
患者様の希望に寄り添うことは大切ですが、無理な適応はかえって“矯正失敗”や“後悔”につながるリスクになるかもしれません。
「前歯だけ矯正したい」「できるだけ安く」「ワイヤーは絶対イヤ」といったケースでは、本当にアライナー矯正が最適なのか慎重に判断する必要があります。
マウスピース矯正が不向きな症例と、見極めポイントを明確にし、患者と医院の双方が納得してスタートできる診断力を養う視点をお伝えします。
マウスピース矯正が不向きな歯並びとは?
マウスピース矯正は、すべての歯並びに適応できるわけではありません。
重度の叢生、骨格的なズレを伴う不正咬合などのケースでは、マウスピース単独での対応が難しいことがあります。
「目立たないから」と無理にアライナー矯正を選んでも、結果として思うように動かず、後悔するケースも少なくありません。
「前歯だけ矯正したい」と希望する患者も多いですが、奥歯の咬合バランスが崩れたままだと、後戻りや噛みにくさの原因になることもあります。
前歯だけの矯正には、短期間で終わるメリットと、咬合全体が安定しないというデメリットの両面があるため、慎重な診断が必要です。
「ワイヤーとどっちがいいか」は症例によって異なり、“やりたい方法”ではなく“治る方法”を選ぶことが、本当の意味での患者満足につながります。
後悔しないための事前チェックポイント
矯正治療で後悔しないために大切なのは、「始める前に何を確認すべきか」を明確にしておくことです。
以下のような事前チェックが抜けていると、「こんなはずじゃなかった」と感じる原因になります。
・装着時間は1日20時間以上だと理解しているか
・取り外し・清掃・保管の管理が面倒だと感じないか
・痛みや違和感が出る可能性があることを知っているか
・症例によっては追加費用・再設計が必要な場合もあると理解しているか
・矯正後の保定や後戻りリスクについて説明を受けているか
「値段が安かったから」「短期間で終わると思ったから」だけで始めた場合、後悔のリスクが高まります。
SNSや知恵袋では「マウスピース矯正 やらなきゃよかった」という声も目にすることがあります。
そうならないためには、事前にメリットとデメリットを冷静に比較し、自分に合った治療法を選ぶ意識が欠かせません。
まとめ
マウスピース矯正は、「手軽」「目立たない」という魅力がある一方で、トラブルが起きたときの対応力によって医院の評価や患者満足度が大きく左右される治療でもあります。
破損・紛失・浮き・痛みなど、よくある問題を「ありがちなこと」で済ませず、事前に想定し、早期に対応することが、信頼される矯正治療には欠かせません。
歯科衛生士の立場では、患者様の表情や小さな一言から異変に気づく機会も多く、声かけがトラブル回避のカギになると実感しています。
「浮いてる気がする」「なんか痛い」など、ちょっとした相談を受けたとき、「それ、よくあるんです」と流すのではなく、すぐに確認・共有し、対応フローにつなげていきます。
そういった小さな積み重ねが、結果的に大きな信頼と継続治療につながるのではないでしょうか。
マウスピース矯正は、装置だけで結果が出るわけではありません。
人の介入があるからこそ、失敗は回避でき、成功に導けるのです。
患者様と同じ目線で、一歩先を見据えた矯正サポートを続けていきたいですね。
トラブル対応や症例に基づく判断ポイントは、日々の臨床の中ではなかなか言語化しづらいものです。
ORTCでは、マウスピース矯正について学べる動画も揃えております。
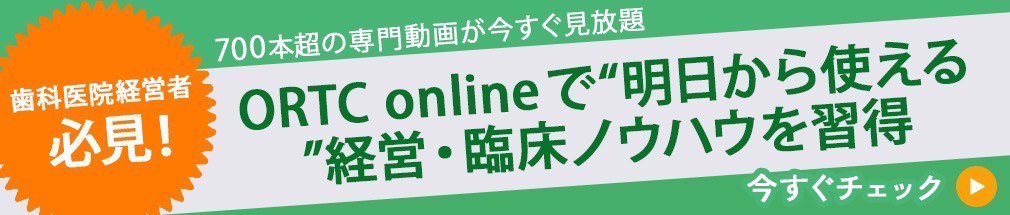
ぜひ、ご覧ください。
よくある質問
Q1:患者から「アライナーがなくなった」と連絡があった場合、まず確認すべきことは?
A1:装着しているアライナーのステージ(何枚目か)、装着期間(日数)、歯の動きの状況を電話で確認しましょう。
一つ前のアライナーへ戻すか、次の段階に進めるか、来院の有無も含め、状況に応じた判断が求められます。
Q2:アライナーが浮いてフィットしないと言われたとき、どう対応すべき?
A2:装着時間の実態やチューイーの使用有無を確認し、原因を整理しましょう。
浮きの部位(前歯/臼歯)に応じて、再装着指導・リフィット・アタッチメント確認など段階的に対応します。
Q3:マウスピース矯正が向かない症例には、どんな特徴がありますか?
A3:著しい骨格性不正咬合、大きな捻転や抜歯を伴う全体矯正、骨の代謝が不安定な症例などは難易度が高くなります。
Q4:患者が「歯が動いていない気がする」と不安を口にした場合、どこを確認すればよい?
A4:クリンチェックと実際の歯列のギャップ、IPRの実施状況、アタッチメントの脱離や形態変化、装着時間などを総合的に見直しましょう。
必要に応じてリプランニングや追加アライナーで再設計も検討します。
Q5:患者が「アタッチメントが取れた」と訴えてきた場合の対応は?
A5:そのアタッチメントが歯の移動にどれだけ関与しているかを確認し、再装着の必要性を判断します。
クリンチェックのデザインと比較し、取れた部位の清掃・接着処理の再確認も行いましょう。
歯科衛生士ライター 原田未祐
歯科医療の現場で役立つ実践的な知識を届けるORTC

ORTCは「笑顔の役に立つ」を理念に、歯科界の知識を共有する場を目指しています。歯科医療の現場で役立つ最新の知識と技術を提供することで、臨床と経営の両面からクリニックの成長を支援します。最先端の技術解説や経営戦略に特化した情報を集約し、歯科医療の現場での成果を最大化。自己成長を追求するためのコンテンツをぜひご活用ください。
無料会員登録
無料動画の視聴、有料動画のレンタルが可能です。歯科業界についてのオンライン・オフラインセミナーへの参加が可能となります。
ORTCPRIME
月額5500円で、 ORTC内のすべての動画を見放題に。臨床の現場に役立つ最新の技術解説や、歯科医院経営の成功戦略を網羅した特別コンテンツをご利用いただけます。 歯科業界の方へ効率的に知識を深めていただける内容です。
ORTC動画一覧
ORTCセミナー一覧
まずは無料会員登録
こちらのリンクより会員登録ページへお進みください。
会員登録はこちら
ORTCPRIMEへのアップグレードも簡単!
登録後は「マイページ」から、ORTCPRIMEにいつでもアップグレード可能です。
 こちらの動画もおすすめです
こちらの動画もおすすめです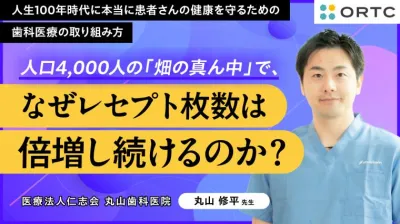 人口4,000人の「畑の真ん中」で、なぜレセプト枚数は倍増し続けるのか?
人口4,000人の「畑の真ん中」で、なぜレセプト枚数は倍増し続けるのか?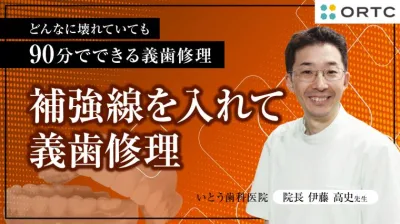 補強線を入れて義歯修理
補強線を入れて義歯修理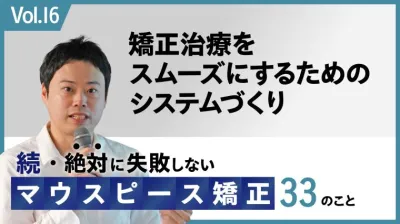 続・ 絶対に失敗しないMP矯正33の事 システムづくり
続・ 絶対に失敗しないMP矯正33の事 システムづくり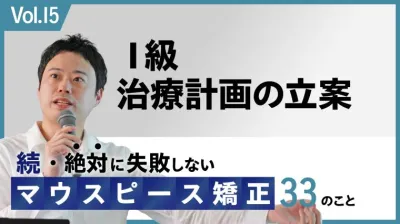 続・ 絶対に失敗しないMP矯正33の事 Ⅰ級 治療計画の立案
続・ 絶対に失敗しないMP矯正33の事 Ⅰ級 治療計画の立案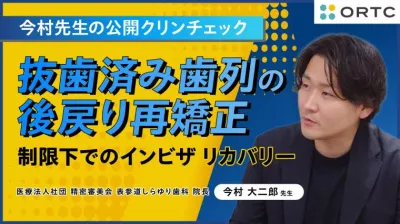 抜歯済み歯列の後戻り再矯正:制限下でのインビザ リカバリー
抜歯済み歯列の後戻り再矯正:制限下でのインビザ リカバリー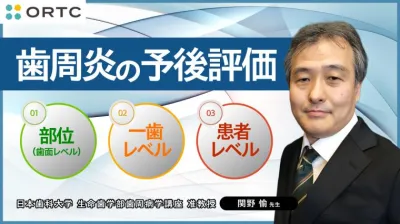 歯周炎の予後評価 1.部位(歯面レベル) 2.一歯レベル 3.患者レベル
歯周炎の予後評価 1.部位(歯面レベル) 2.一歯レベル 3.患者レベル 歯周病の新分類
歯周病の新分類 チェアサイドでのご提案を7ステップで完全マスター Part3
チェアサイドでのご提案を7ステップで完全マスター Part3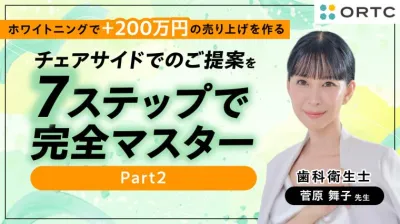 チェアサイドでのご提案を7ステップで完全マスター Part2
チェアサイドでのご提案を7ステップで完全マスター Part2 チェアサイドでのご提案を7ステップで完全マスター Part1
チェアサイドでのご提案を7ステップで完全マスター Part1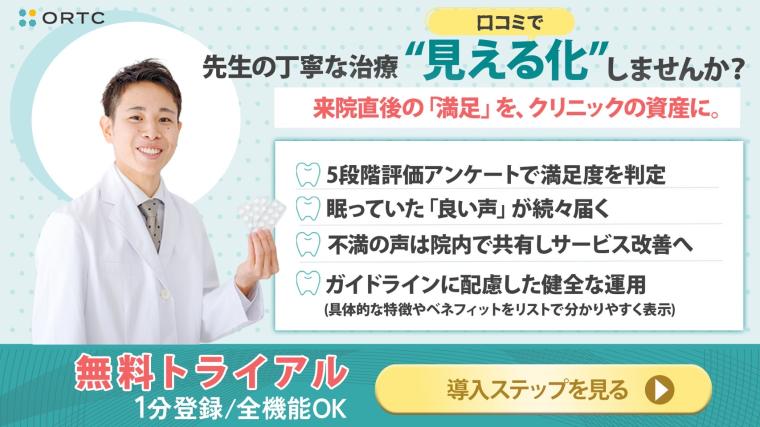

 マウスピース矯正のトラブルは、起こってしまったあとも重要になります。
マウスピース矯正のトラブルは、起こってしまったあとも重要になります。