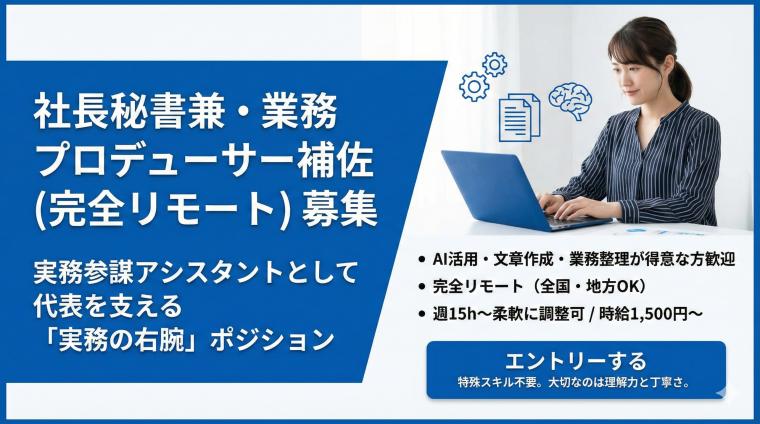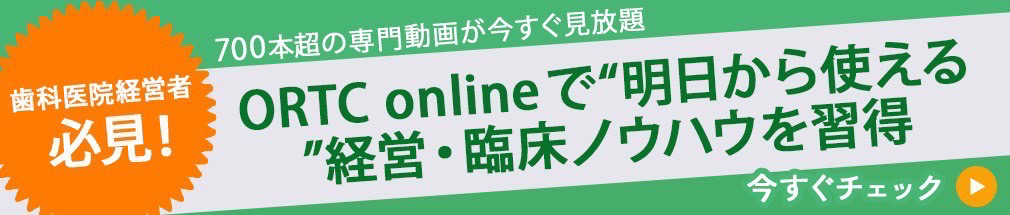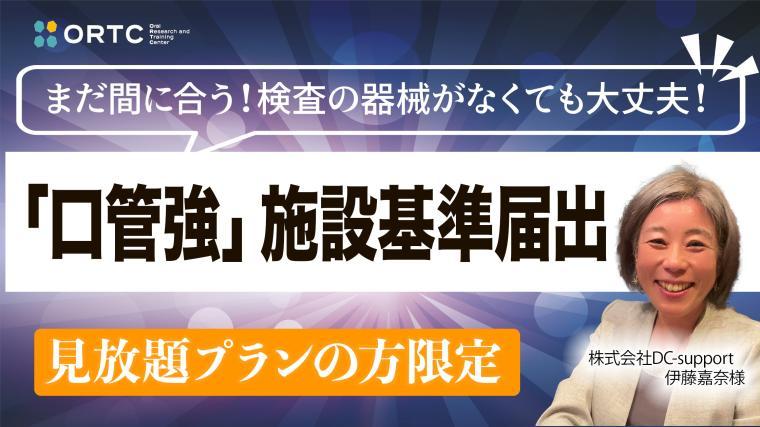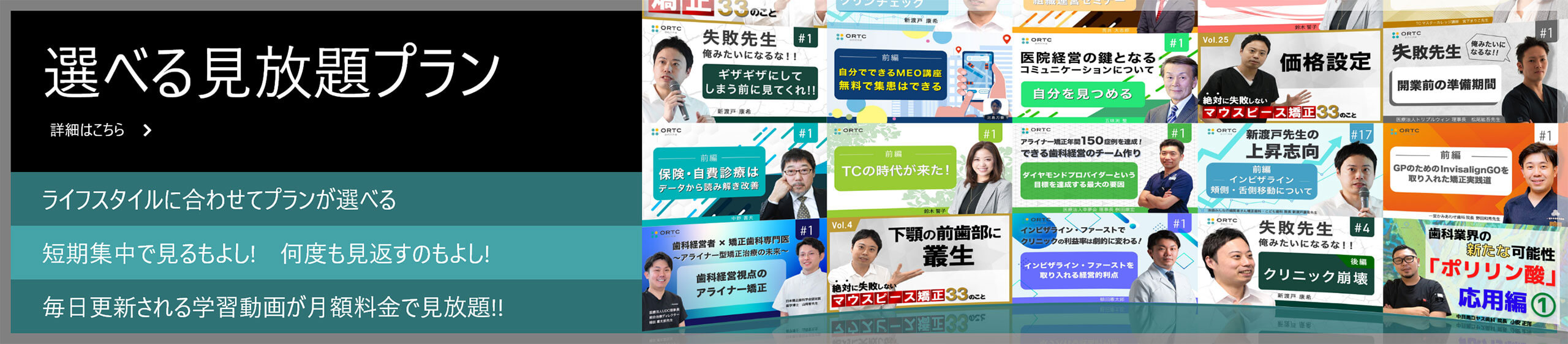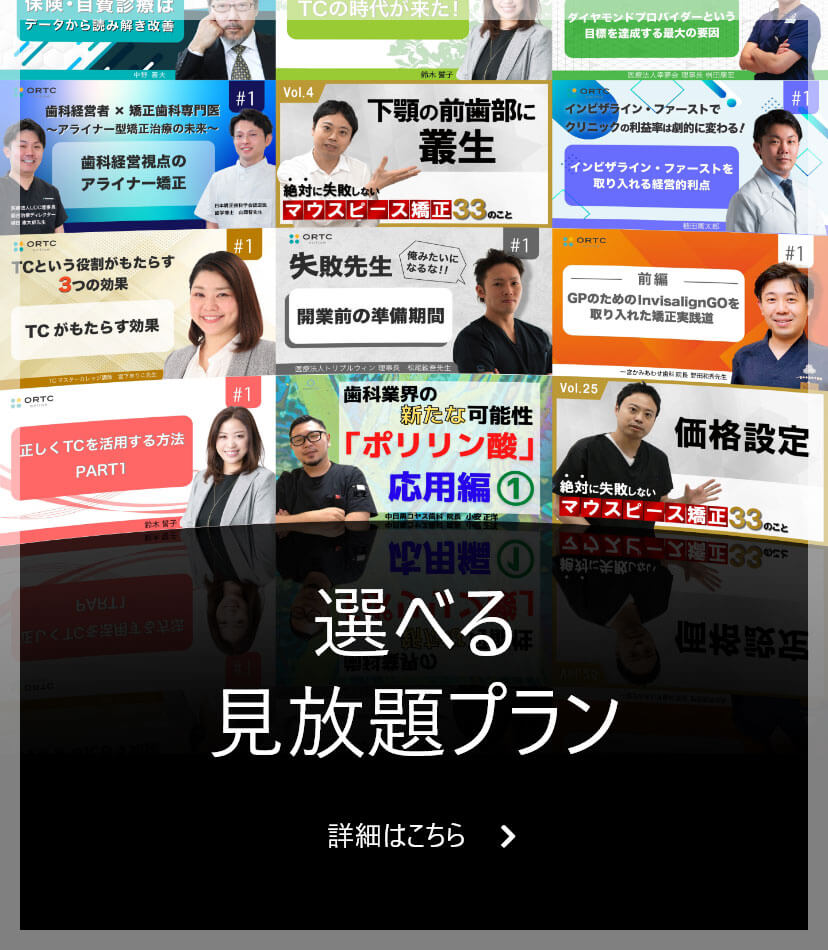超高齢社会を迎えた日本の歯科医療において、「オーラルフレイル(口腔機能の虚弱化)」への対策は、もはや避けては通れない重要テーマです。
患者様の健康寿命を延ばし、要介護状態への移行を防ぐうえで、歯科医院が果たす役割はますます大きくなっています。
2024年には日本老年歯科医学会からオーラルフレイルに関する新たな定義とステートメントが公表され、その注目度はさらに高まっています。
本記事では、この最新の動向を踏まえ、オーラルフレイルの基礎知識から、臨床現場で明日から実践できる具体的な「評価方法」「予防・改善策」までを網羅的に解説します。
高齢患者様を診るすべての歯科医療従事者にとって、必読の内容です。
オーラルフレイルとは?

オーラルフレイル最新定義と重要性は以下のとおりです。
それぞれ解説していますので、頭に入れておきましょう。
オーラルフレイルの基本概念
オーラルフレイルとは、「老化に伴う口腔機能の軽微な低下や食の偏りなどを含み、身体のフレイル(虚弱)へと繋がる複合的な事象」として定義されています。
単なる「滑舌の低下」「食べこぼし」といった個別の症状ではなく、口腔機能の低下が連鎖的に進行するプロセスであることが重要なポイントです。
この連鎖は段階的に進行し、まず社会性の低下から始まります。
人との交流が減少することで口腔への関心が薄れ、口腔機能の軽微な低下が生じます。
その結果、食品の多様性が低下し、栄養状態の悪化を招きます。
さらに栄養状態の悪化により口腔機能がより一層低下し、最終的に全身のフレイルへと発展していくのです。
このプロセスを理解することで、早期発見・早期介入の重要性が明確になります。
【2024年最新情報】日本老年歯科医学会の新定義
2024年に公表された新定義では、従来の概念に加えて重要な視点が新たに追加されました。
まず、口腔の健康リテラシーの低下が重要な要素として位置づけられました。
これは、口腔ケアの重要性に対する認識や実践力の低下を指します。
また、社会性との関連についても新たに注目され、社会的孤立や人との交流減少が口腔機能低下の引き金となることが明確にされ、多面的評価の必要性が強調されるようになっています。
機能面だけでなく心理的・社会的側面も含めた総合的な評価が求められるようになりました。
この新定義により、オーラルフレイル対策には単に機能訓練を行うだけでなく、患者様の生活背景や社会的環境も考慮した包括的なアプローチが必要であることが明確になりました。
「口腔機能低下症」との違いと関連性
臨床現場でよく混同されがちな「口腔機能低下症」とオーラルフレイルの違いを整理しておきましょう。
口腔機能低下症は保険診療における「疾患名」として位置づけられ、器質的・機能的な口腔機能の低下を客観的に診断するものです。
7つの検査項目による定量的評価を行い、治療・管理の対象となります。
一方、オーラルフレイルは機能的・心理的・社会的側面を含む「状態」を指し、予防から重度機能低下まで幅広い概念を包含しています。
主観的評価も含めた多面的アプローチが特徴で、予防・啓発の対象として捉えられていることが現状です。両者は相互に関連し合い、口腔機能低下症の検査項目はオーラルフレイルの客観的評価にも活用できます。
詳しく知りたい方はこちら!
ORTC独占セミナーを配信中!
テーマ名:新定義!オーラルフレイルと義歯治療
講師名:ハイライフデンチャーアカデミー
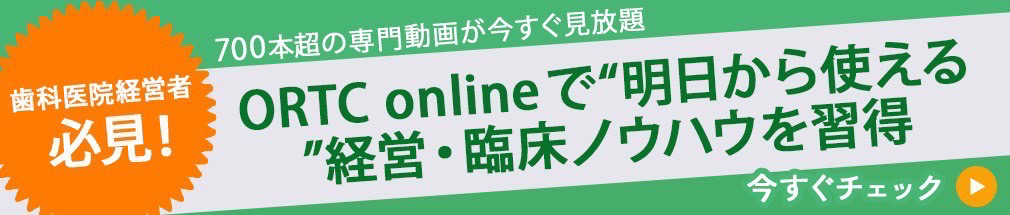
なぜ今、歯科医院でオーラルフレイル対策が求められるのか?

なぜ今、歯科医院でオーラルフレイル対策が求められるのかについて解説すると、以下のようになります。
・健康寿命の延伸と要介護予防への貢献
・地域包括ケアシステムにおける歯科の役割
それぞれ詳しくみていきましょう。
健康寿命の延伸と要介護予防への貢献
オーラルフレイルが進行すると、「フレイル・ドミノ」と呼ばれる負の連鎖が始まります。
この連鎖は、まず口腔機能の低下により硬い食品の摂取が困難になることから始まります。
その結果、食品多様性の低下を招き、栄養バランスの悪化につながります。
栄養状態の悪化は筋肉量・筋力の低下を引き起こし、サルコペニア(筋肉減少症)を発症させます。
さらに進行すると身体機能全体が低下し、全身のフレイルへと発展し、最終的に要介護状態へのリスクが大幅に増大します。
この連鎖を断ち切るためには、最初の段階である口腔機能の低下を早期に発見し、適切な介入を行うことが極めて重要です。
実際、口腔機能が良好に保たれている高齢者は、そうでない高齢者と比べて要介護認定率が約30%低く、認知機能の低下リスクが約40%低く、死亡リスクが約20%低いという研究結果が報告されています。
地域包括ケアシステムにおける歯科の役割
地域包括ケアシステムにおいて、歯科医院は単独で存在するのではなく、医科・介護・福祉の各専門職と連携する必要があります。
この多職種連携において、口腔機能の評価と管理は重要な「共通言語」となります。
具体的には、医科との連携では嚥下機能評価や低栄養状態の早期発見が重要な役割となり、介護との連携ではADL(日常生活動作)の維持・向上への貢献が期待されます。
また、福祉との連携では社会参加促進やQOL向上のサポートが求められます。
かかりつけ歯科医として、患者様の口腔機能を継続的に評価・管理することで、地域全体の健康増進に貢献できるのです。
明日からできる!オーラルフレイルの評価方法

オーラルフレイルの評価方法はいくつかありますが、ここでは代表的な評価方法をまとめました。
臨床において、あまり使わない歯科医院もあるかと思いますが、これを機に振り返っておきましょう。
問診で気づく ―オーラルフレイル・チェックリスト
特別な機器がなくても、問診によってオーラルフレイルのリスクを評価できます。
代表的なチェックリストとして、イレブン・チェック(11項目)があります。
これは、半年前に比べて硬いものが食べにくくなった、お茶や汁物でむせることがある、義歯を使用している、口の乾きが気になる、半年前に比べて外出が少なくなった、さきイカ・たくあんくらいの硬さの食べ物が噛めない、1日に2回以上は歯を磨く、1年間に歯科医院に健診を受けに行く、舌の力が弱くなった気がする、口の汚れや臭いが気になる、食べこぼしをするようになった、という11の項目で構成されています。
評価基準としては、0-2項目に該当する場合は問題なし、3-5項目の場合は軽度リスク、6項目以上の場合は高リスクと判定されます。
この簡単なチェックリストにより、患者様自身に口腔機能の変化を認識してもらい、早期発見・早期介入につなげることができます。
客観的指標による評価
より詳細な評価を行う場合は、客観的指標を活用します。
咀嚼機能評価では、グミゼリー咀嚼能力測定として市販のグミゼリーを20回咀嚼後、粉砕状態を評価する方法があります。
また、咀嚼能力測定装置を用いてグルコース溶出量や色彩変化による定量的評価も可能で、健常高齢者の平均値と比較評価を行います。
舌口唇運動機能評価では、オーラルディアドコキネシスとして「パ」「タ」「カ」の1秒間の発音回数を測定します。
基準値は各音6回/秒以上とされています。また、舌圧測定器を用いた最大舌圧の測定も有効で、基準値は30kPa以上です。
嚥下機能評価では、反復唾液嚥下テスト(RSST)として30秒間の唾液嚥下回数を測定し、基準値は3回以上とされています。
さらに、水飲みテストでは30mlの水を飲み込む際の所要時間と症状観察を行い、基準値は5秒以内でむせなしとされています。
口腔機能低下症の7項目との関連付け
保険診療の「口腔機能低下症」の検査項目は、オーラルフレイルの客観的評価にも活用できます。
口腔機能低下症の7項目は、口腔衛生状態不良、口腔乾燥、咬合力低下、舌口唇運動機能低下、低舌圧、咀嚼機能低下、嚥下機能低下で構成されています。
これらの項目のうち3項目以上に該当する場合、口腔機能低下症として診断され、保険診療による管理が可能になります。
臨床で実践するオーラルフレイルの予防・改善策

オーラルフレイルの予防・改善には三つのアプローチが重要です。
まず口腔機能訓練では、パタカラ体操(1日3回各10回)やあいうべ体操(1日30回)により舌口唇運動機能と口腔周囲筋を強化します。
ガム咀嚼訓練(左右各2分間、1日2-3回)は咀嚼筋力向上と唾液分泌促進に効果的です。重度例では舌接触補助床(PAP)などの専門的介入も検討します。
次に補綴治療は、咀嚼機能回復による食品多様性向上、食事への意欲向上、社会参加促進など多面的効果をもたらします。
治療計画では患者の全身状態を考慮し、段階的アプローチと継続的メンテナンスが重要です。
最後に多職種連携では、管理栄養士との連携により咀嚼能力に応じた食事形態を提案し、医科・介護・薬剤師との連携で包括的ケアを実現します。
歯科医院での評価・診断から始まり、専門職紹介、定期的カンファレンス、継続的フォローアップという連携フローにより、効果的なオーラルフレイル対策が可能になります。
まとめ
本記事では、2024年の新定義を踏まえたオーラルフレイル対策について、評価方法から具体的な予防・改善策までを解説しました。
オーラルフレイルへの介入は、高齢患者様の口腔の健康を守るだけでなく、全身の健康、そしてQOLの維持・向上につながる重要な取り組みです。
実践のポイントとして、簡単なチェックリストから始める問診の活用、客観的指標による詳細な機能評価、患者様の生活背景を考慮した個別対応、多職種との連携による包括的アプローチが重要です。
まずは、明日からの臨床で患者様への簡単な問診から始めてみてください。
オーラルフレイルの早期発見・早期介入により、患者様の健康寿命の延伸に貢献できるはずです。
この記事が、先生の歯科医院における高齢者歯科診療をさらに発展させる一助となれば幸いです。
もっと詳しく学びたい!
それなら場所と時間に捉われないORTCがおすすめ。

参考文献
https://www.tmd.ac.jp/dent_hospital/news/211214/index.html
https://www.city.shiki.lg.jp/soshiki/24/26372.html
https://www.ncgg.go.jp/hospital/navi/39.html
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsg/31/4/31_412/_pdf
Q&A
Q1. オーラルフレイルと口腔機能低下症の違いは何ですか?
A1. オーラルフレイルは機能的・心理的・社会的側面を含む「状態」で、予防から重度機能低下まで幅広い概念を包含しています。
一方、口腔機能低下症は保険診療における「疾患名」として位置づけられ、7つの検査項目による客観的な診断を行います。
オーラルフレイルは予防・啓発の対象であり、口腔機能低下症は治療・管理の対象という違いがあります。
両者は相互に関連し合い、口腔機能低下症の検査項目はオーラルフレイルの客観的評価にも活用できます。
Q2. 2024年の新定義で何が変わったのですか?
A2. 2024年に日本老年歯科医学会から公表された新定義では、従来の概念に加えて重要な視点が追加されました。
具体的には、「口腔の健康リテラシーの低下」(口腔ケアの重要性に対する認識や実践力の低下)、「社会性との関連」(社会的孤立や人との交流減少が口腔機能低下の引き金となる)、「多面的評価の必要性」(機能面だけでなく心理的・社会的側面も含めた総合的な評価)が強調されました。
これにより、単なる機能訓練だけでなく、患者の生活背景や社会的環境も考慮した包括的なアプローチが必要であることが明確になっています。
Q3. イレブン・チェックの評価基準と活用方法を教えてください。
A3. イレブン・チェックは11項目の簡単な質問でオーラルフレイルのリスクを評価できるツールです。
評価基準は、0-2項目該当で「問題なし」、3-5項目で「軽度リスク」、6項目以上で「高リスク」と判定されます。
質問内容には「半年前に比べて硬いものが食べにくくなった」「お茶や汁物でむせることがある」「口の乾きが気になる」などが含まれています。
特別な機器が不要で、患者自身に口腔機能の変化を認識してもらい、早期発見・早期介入につなげることができる実用的なツールです。
Q4. パタカラ体操とあいうべ体操の具体的な実施方法は?
A4. パタカラ体操は舌口唇運動機能の向上を目的とし、「パ」「タ」「カ」「ラ」を明瞭に発音する訓練です。
1日3回、各10回ずつ実施し、指導の際は鏡を見ながら口の動きを意識させることがポイントです。
あいうべ体操は口腔周囲筋の筋力向上と鼻呼吸の促進を目的とし、「あ」「い」「う」「べ」の口の形を各1秒間保持し、1日30回実施します。
指導のポイントは、大きく口を動かし表情筋全体を使うことです。両体操とも患者が自宅で継続しやすく、特別な器具も不要な効果的な訓練法です。
Q5. 多職種連携における歯科の具体的な役割と連携フローは?
A5. 歯科は多職種連携の中核として、口腔機能評価を通じて全身の健康管理に貢献します。
管理栄養士とは咀嚼能力に応じた食事形態の提案や栄養指導で連携し、医科とは嚥下機能問題時の紹介や誤嚥性肺炎リスク評価で協働します。
介護分野ではケアマネージャーと日常の口腔ケア継続について連携し、薬剤師とは口腔乾燥を引き起こす薬剤の確認を行います。
連携フローは、①歯科医院での評価・診断、②必要に応じた専門職への紹介、③定期的な情報共有・カンファレンス、④継続的なモニタリング・フォローアップの4段階で進行し、包括的なケアを実現します。
歯科専門ライター 萩原すう
歯科医療の現場で役立つ実践的な知識を届けるORTC

ORTCは「笑顔の役に立つ」を理念に、歯科界の知識を共有する場を目指しています。歯科医療の現場で役立つ最新の知識と技術を提供することで、臨床と経営の両面からクリニックの成長を支援します。最先端の技術解説や経営戦略に特化した情報を集約し、歯科医療の現場での成果を最大化。自己成長を追求するためのコンテンツをぜひご活用ください。
無料会員登録
無料動画の視聴、有料動画のレンタルが可能です。歯科業界についてのオンライン・オフラインセミナーへの参加が可能となります。
ORTCPRIME
月額5500円で、 ORTC内のすべての動画を見放題に。臨床の現場に役立つ最新の技術解説や、歯科医院経営の成功戦略を網羅した特別コンテンツをご利用いただけます。 歯科業界の方へ効率的に知識を深めていただける内容です。
ORTC動画一覧
ORTCセミナー一覧
まずは無料会員登録
こちらのリンクより会員登録ページへお進みください。
会員登録はこちら
ORTCPRIMEへのアップグレードも簡単!
登録後は「マイページ」から、ORTCPRIMEにいつでもアップグレード可能です。
 こちらの動画もおすすめです
こちらの動画もおすすめです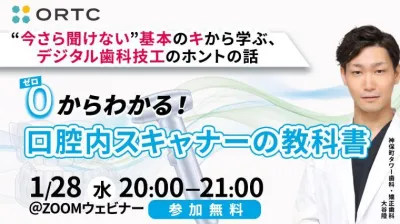 “今さら聞けない”基本のキから学ぶ、デジタル歯科技工のホントの話『ゼロからわかる、口腔内スキャナーの教科書』
“今さら聞けない”基本のキから学ぶ、デジタル歯科技工のホントの話『ゼロからわかる、口腔内スキャナーの教科書』 歯科医師のキャリア戦略 ― 勤務医・開業・M&A・資産形成まで、後悔しない選択とは ―
歯科医師のキャリア戦略 ― 勤務医・開業・M&A・資産形成まで、後悔しない選択とは ―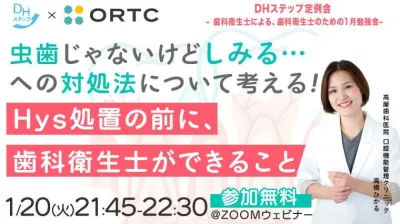 虫歯じゃないけどしみる…への対処法について考える Hys処置の前に、歯科衛生士ができること
虫歯じゃないけどしみる…への対処法について考える Hys処置の前に、歯科衛生士ができること 「TBIが変われば患者が変わる」 自費TBI成功マインド
「TBIが変われば患者が変わる」 自費TBI成功マインド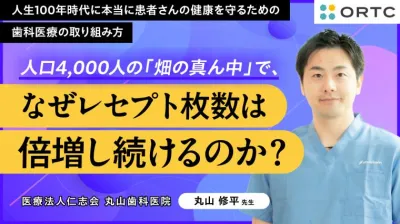 人口4,000人の「畑の真ん中」で、なぜレセプト枚数は倍増し続けるのか?
人口4,000人の「畑の真ん中」で、なぜレセプト枚数は倍増し続けるのか?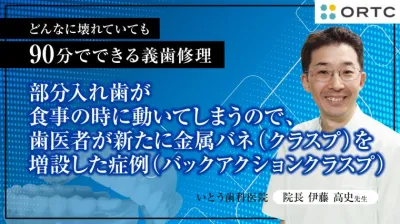 部分入れ歯が食事の時に動いてしまうので、歯医者が新たに金属バネ(クラスプ)を増設した症例(バックアクションクラスプ)
部分入れ歯が食事の時に動いてしまうので、歯医者が新たに金属バネ(クラスプ)を増設した症例(バックアクションクラスプ)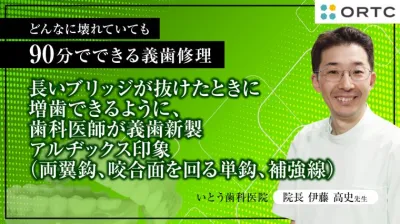 長いブリッジが抜けたときに増歯できるように、歯科医師が義歯新製 アルヂックス印象(両翼鈎、咬合面を回る単鈎、補強線)
長いブリッジが抜けたときに増歯できるように、歯科医師が義歯新製 アルヂックス印象(両翼鈎、咬合面を回る単鈎、補強線)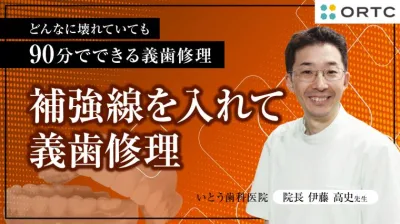 補強線を入れて義歯修理
補強線を入れて義歯修理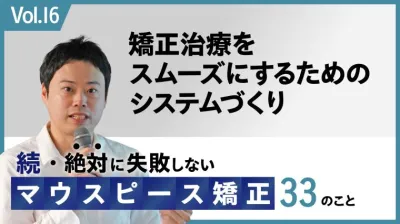 続・ 絶対に失敗しないMP矯正33の事 システムづくり
続・ 絶対に失敗しないMP矯正33の事 システムづくり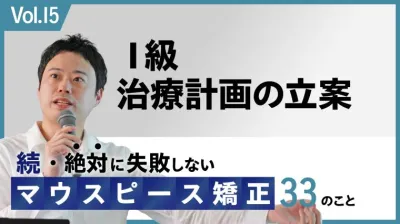 続・ 絶対に失敗しないMP矯正33の事 Ⅰ級 治療計画の立案
続・ 絶対に失敗しないMP矯正33の事 Ⅰ級 治療計画の立案