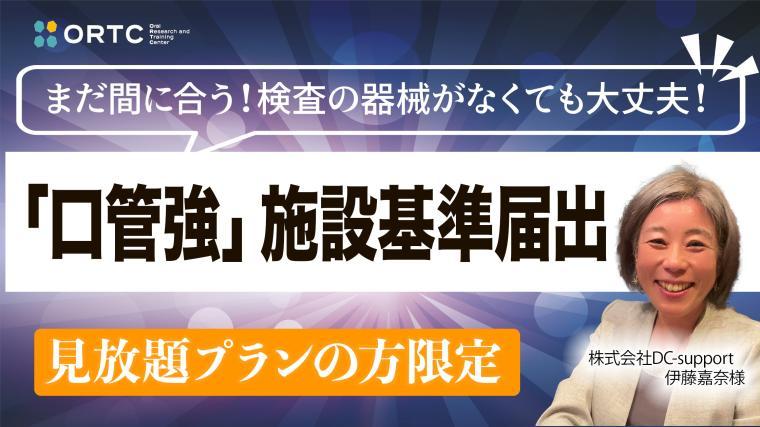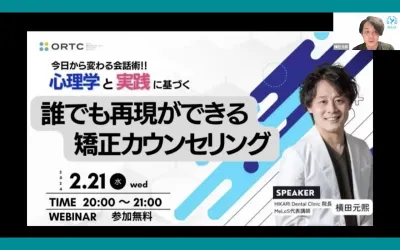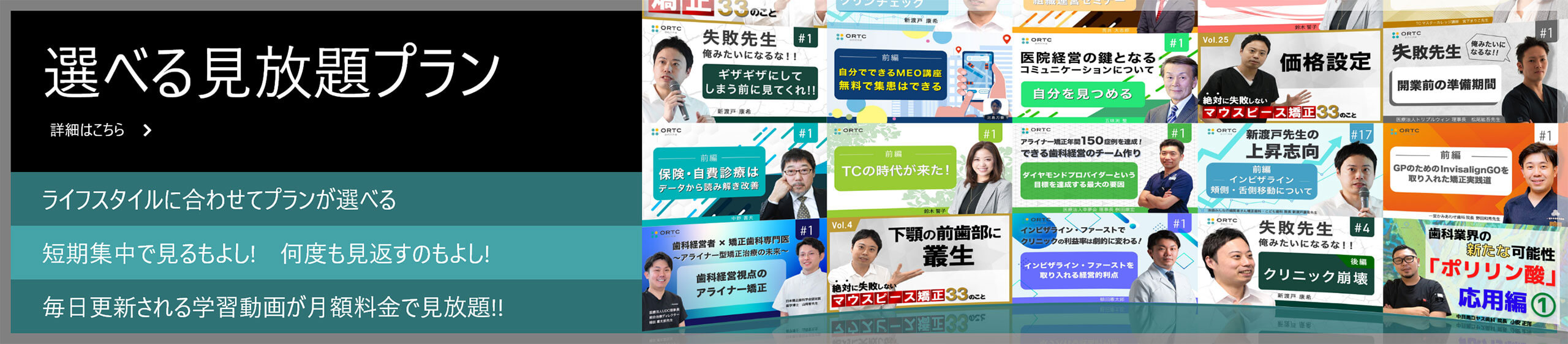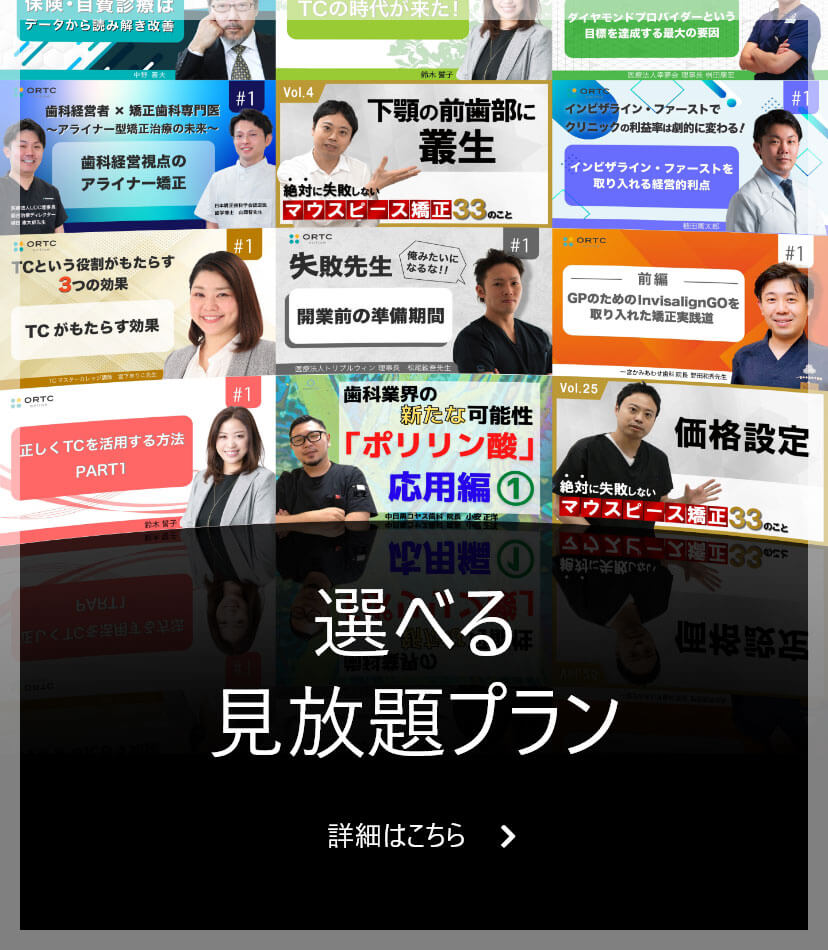虫歯や歯周病なでおではを失った時に、どのような方法でその失ってしまった機能を補っていくのか、患者さんに対して分かりやすく説明できますか?
歯を失った際に対応する補綴物といえば、ブリッジ、インプラント、そして入れ歯の三択になるでしょう。
一昔前に比べればインプラントを選ばれる方も増えてきてはおりますが、平成28年度に行われた厚生労働省の調査(※1)によればインプラントを選択している人は全体のおよそ2%なのに対し、ブリッジは35%とかなりの割合の人がブリッジを選択していることが分かります。
ブリッジを選ぶ方のお声を聞いてみると、ブリッジには保険が適用されること、インプラントのように手術が必要でないこと、入れ歯のように着脱式でないことから安定性が高いことにメリットを感じて選択されているようです。
一方で、入れ歯であれば隣在歯を削らずに済むというメリットがありますし、インプラントであれば自然な見た目や噛み心地を得ることができます。
この記事ではブリッジの適応症から設計など今更聞けないポイントや、インプラントと義歯と比較した場合のメリットデメリットについて解説していきます。
<この記事で分かること>
1、ブリッジの適応症
2、設計・材料選択の最新トレンド
3、支台歯形成の臨床ポイント
4、補綴後の清掃指導とメインテナンス
5、インプラント・義歯との比較
ぜひ、日ごろの臨床にお役立てくださいね。
1、ブリッジの適応症

ブリッジとは、歯を失った場所の両隣の歯を削って土台を作り、その歯を支えとして橋を渡すように人工歯(ポンティック)を固定して欠損部分を補う治療方法です。
保険治療でブリッジを行う場合には以下のような規定が存在します。
1)欠損歯は連続して2歯まで(ただし、1~2番目の欠損の場合、連続して4歯まで可能)
2)支台歯の状態が良く、最低2年間は問題が出ないと診断された場合
支台となる歯は動揺がなくしっかりしていて、歯周病などの問題がない状態が理想的です。
ブリッジは取り外しをしない補綴物であることから違和感が少ないという長所がありますが、その分支えとなる両隣の歯に噛み合わせの力の負担がかかります。
ブリッジ治療を成功させるためには、支えとなる歯の状態や噛み合わせなどについて考え、力学的に無理のないブリッジを設計することが重要です。
また、地方厚生(支)局が2007年に発表した「ブリッジの考え方」(※2)によると、ブリッジの適用条件は以下の通りです。
1)支台歯となる歯がブリッジによる補綴治療に適した本数存在していること
2)支台歯となる歯は作成するブリッジの咬合負担等に十分耐え得る歯根および骨植であり、歯軸方向、位置、排列状態も適切であること
3)支台歯は支台装置の作成が可能であること
4)補綴すべき欠損部がブリッジによる治療を行うのに支障がないこと
5)歯の欠損部の補綴装置にブリッジに適した配置、排列および構造を与え得ること
6)歯の欠損部の歯槽堤の退縮の程度および状態が、ブリッジによる治療を行うのに支障がないこと
7)対合歯との咬合状態がブリッジによる治療を行うのに支障がないこと
8)口腔内の衛生状態がブリッジによる治療を行うのに支障がないこと
9)患者の職業・習慣、食生活、受療条件などがブリッジによる治療を行うのに支障がないこと
ブリッジにかかる咬合力はその全てを支台歯が受けることになります。この咬合力は支台歯から歯根膜を通じて歯槽骨に伝わります。
ブリッジにかかる咬合力は支台歯自体に加わるものとポンティックに加わるものが掛け合わさったものとなります。
これらの咬合力に対してブリッジが変形したり破折することなく機能することがブリッジの設計に求められます。
ブリッジの設計において大切なのは、全体の設計と支台歯の状態の診断です。
ブリッジには4つの種類があります。
①固定性ブリッジ
一般的によく用いられる支台歯とブリッジがセメントで接着されているブリッジです。
支台歯となる両隣の歯を大きく削る必要があるものの、固定されているため安定性があり自然な感覚で噛むことができます。
②半固定性ブリッジ
一部のポンティックと支台歯を「キーアンドキーウェイ」というスライド型のアタッチメントで連結したブリッジです。
キーアンドキーウェイは歯を連結しないため、連結による身体の負担や不調を無くし、本来の生体システムの動きをしてくれます。
③接着ブリッジ
通常のブリッジは両隣の歯を大きく削る必要がありますが、接着ブリッジは両隣もしくはどちらか片方の歯の表面をわずかに削り接着することで固定するブリッジです。
通常の固定性ブリッジと比較すると外れやすくはなりますが、健全な歯を削る量が少なく、抜髄の必要がないのが大きなメリットです。
④可撤性ブリッジ
ブリッジの全部もしくは一部を取り外すことができるブリッジです。患者さん自身が取り外すことが出来るため、他のブリッジに比べて清掃しやすい点がメリットです。
\詳しく学ぶなら、気軽に学べるORTCon-lineがおすすめ!/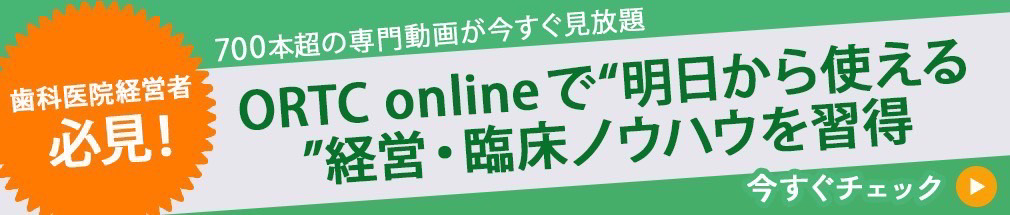
2、設計・材料選択の最新トレンド

ブリッジの支台歯は失った歯の分まで咬合圧を負担することになります。そのため、噛めば噛むほど歯根にダメージが蓄積し、歯根破折のリスクが高まります。
口腔内でそれぞれの歯が持つ機能圧に対する負担能力の大きさはそれぞれの歯の歯根膜の表面積に比例すると考えられており、ブリッジの設計において指標となる物理力学的な計算方法があります。
①Duchangeの指数
Duchangeの指数とは、ブリッジの設計において使用される係数で、抵抗性の良否を判定するために用いられます。
各歯の歯根表面積をもとに、咬合圧に対する支台歯の抵抗性とポンティックの疲労を数値化して考えることができます。
②Anteの法則
Anteの法則とは、固定性ブリッジの制作において支台歯のセメント質表面積の総和は補綴される欠損歯の総和と同等かそれ以上でなければならないという考え方です。
歯周病に罹患して歯茎が下がっていると支台歯の歯根膜の量は減少するため、ブリッジを実施するにはかなり不利となります。
このように、支えとなる歯の状態や噛み合わせの状況を考え、どの形態のブリッジが一番歯に負担をかけずに済むか、力学的に無理がないかを考えて設計することがブリッジ治療の成功のカギとなります。
また、隣在歯の欠損によって隣接面接触点が消失すること、根管治療を行なった歯の咬合力負担能力は健全歯に比べて低下すること、歯周疾患に罹患している歯は歯槽骨の吸収程度に比例して咬合力負担が著しく低下することなどを考えた設計を行う必要があります。
ブリッジの素材として保険が適用されるのは「銀歯」と「硬質レジン前装冠」のみでしたが、2018年4月から「高強度硬質レジンブリッジ」が保険適用となったことで、白い歯にすることができる適用範囲が広がりました。
高強度硬質レジンブリッジは臼歯部の大きな咬合力に耐えられる高強度のコンポジットレジンとグラスファイバーを用いることで、歯科用金属を使用せずにブリッジを作ります。
噛み合わせにより大きな応力がかかるブリッジの連結部にグラスファイバーを用いることにより、さらにブリッジ強化が図られています。
公益社団法人日本補綴歯科学会がまとめた資料(※3)によると、高強度硬質レジンブリッジを成功させるポイントは以下の通りです。
適応症の判断
第二小臼歯の欠損に対して、第一小臼歯および第一大臼歯を支台歯とする症例
(上下顎両側の第二大臼歯が全て残存し、左右の咬合支持が確保されていること)
禁忌症
過小な支台歯高径、顕著な咬耗(ブラキシズム)
適応を控えるべき症例
部分床義歯の支台歯、高度な審美性の要望
安全な症例
保持力を得るために十分な歯冠高径があり、対合歯との適切なクリアランスが確保できる
補助的保持形態が必要ない
過度な咬合圧や応力が加わらない
高強度硬質レジンブリッジは比較的強度も強く、また金属を使用していないため金属アレルギーの方にも安心しておすすめすることができます。
天然の歯の硬さに近いため、噛み合う歯にダメージを与えにくいこともメリットです。
一方、セラミックや金属に比べると強度が劣るため割れる可能性があり、強度を保つために歯をたくさん削る必要があります。
メリットデメリットをそれぞれ考えた上で、患者さんの状態にあった方法を選択しましょう。
\詳しく学ぶなら、気軽に学べるORTCon-lineがおすすめ!/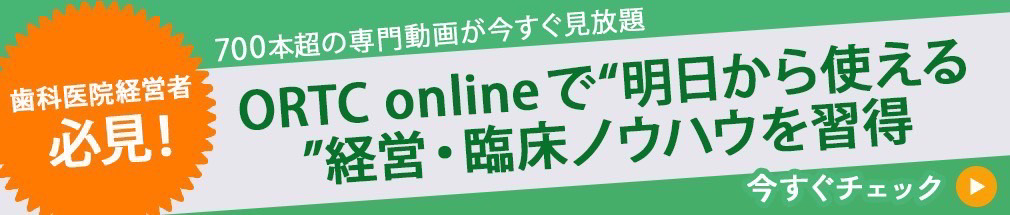
3、支台歯形成の臨床ポイント
 支台歯形成とは、補綴物を被せる際の土台となる歯の形態を形成することです。
支台歯形成とは、補綴物を被せる際の土台となる歯の形態を形成することです。
支台歯形成を行う際には歯肉の炎症をコントロールしておくことが求められます。
歯肉が腫れていたり荒れている状態で形成を行なって印象すると、フィニッシュラインのズレや不適合に繋がります。
形成印象前の適切な圧排はもちろん、歯周病初期治療やブラッシング指導を行うことで口腔内の状況をコントロールできるよう患者さんにお伝えしておきましょう。
支台歯形成の基本として念頭におくことは、
①抵抗形態と保持形態
(1)軸面高さをなるべく高くすること
(2)軸面面積は広く形成すること
(3)修復物との接触面積を大きくするためにも歯と相似形にすること
(4)着脱方向を前歯は歯冠軸、臼歯は咬合平面に垂直な方向にすること
(5)テーパーを2~5°で適度な粗さに仕上げること(難しい場合は適切なグルーブ、ボックス、ホールを形成して離脱を防ぐこと)
②補綴物の十分な強度
③良好な適合性と確実な辺縁封鎖
④審美修復に必要な歯質削除
⑤歯質の保護
咬合力によって補綴物が壊れないようにするためにも、歯質をなるべく残して形成することも必要とされています。
過度な歯質削除はリテンションおよびレジスタンスの低下を生じさせ、過度のテーパーや短い歯冠高径になりやすくなるため注意が必要です。

また、支台歯形成を上手く行うには基本的な手順通りに進めることも成功の秘訣です。基本となる手順は以下の通りです。
①咬合面または切縁
②頰側
③舌側
④隣接面
⑤隅角部修正
アンダーカットがないか確認しながら隅角部を丸めます。
⑥歯肉縁下形成
⑦仕上げ
全体の削合を終えたら、過度になっている部位がないように全ての角を丸く仕上げます。
急がば回れとも言いますが、基本に立ち返ってみることで見えてくることもあります。
一度初心に戻って手順を振り返ってみて下さいね。
4、補綴後の清掃指導とメインテナンス
歯科医療者として、ブリッジをセットして「はい、おしまい」とは行きません。
治療期間を経てやっとブリッジが入って一安心、もうしばらく歯医者に来なくて済む!と思われる患者さんも多いと思いますが、ブリッジも他の治療と同じく二次う蝕の可能性があることを伝え、せっかく時間とお金をかけて噛めるようになったのですから、これからはこのブリッジが悪くならないよう守って行きましょう!と声をかけて、ご自宅で行なって頂くケア方法について清掃指導を行いましょう。
ブリッジに対して指導する清掃用具は主にこの二つです。
スーパーフロス
スーパーフロスとは、支台歯とポンティックの間を通すために先端が固く加工され、中央がスポンジ状になったブリッジ用のフロスのことです。
ポンティックの形状にもよりますが、支台歯とポンティックの間だけでなくポンティックの底面も通るようであれば通すよう指導します。
歯間ブラシ
歯間ブラシはゴムのタイプと毛のタイプがありますが、毛のタイプの方が清掃性が高いため、指導時にお口にあったサイズと共に毛のタイプを使うようお伝えしましょう。
ブリッジ=これを使う!というわけではなく、患者さんの手先の器用さやブリッジが入っている場所、ブリッジの形状を考えてどの清掃用具を選択するか考えていきましょう。
ブリッジは構造上どうしても汚れが溜まりやすく、二次う蝕だけでなく歯周病になってしますリスクも高くなります。
定期的なメインテナンスでお口の健康寿命が伸ばせることを患者さんに伝え、状況に応じたメインテナンス期間を設定しましょう。
また、強い咬合力がかかると支台歯にかかる負担が大きくなり破損や破折に繋がります。
夜間の歯ぎしりや食いしばりから守るためにマウスピースを使用し、ブリッジが安全に機能するよう守っていきましょう。
5、インプラント・義歯との比較
インプラントは高額なものなので一番寿命も長いはず、と安易に考えてしまいがちですが、日本補綴学会が2008年にまとめた「歯の欠損の補綴歯科診療ガイドライン2008」(※4)によると「1歯の中間欠損に対して、5年生存率でみると、インプラントとブリッジで差はなく、機能的にもインプラントが有効であるというエビデンスは存在していない」とまとめられています。
歯を失った際、ブリッジ、インプラント、義歯のどれを選択するのかは患者さんの今後のライフスタイルや求める機能によって考えていく必要があります。
ブリッジ
<メリット>
・治療期間が短い
・鍵などがないため比較的見た目がよい
・固定式のため違和感が少ない
<デメリット>
・両隣の歯を削る必要がある
・両隣の歯に負担がかかる
・構造上汚れが溜まりやすい
インプラント
<メリット>
・隣接する歯に影響を与えずに治療ができる
・顎の骨に固定されるためブリッジや入れ歯に比べて自然な咀嚼感が得られる
・硬い食べ物もよく噛める
・見た目が美しい
<デメリット>
・外科処置を伴う
・骨量が不足している場合、骨造成などの治療が必要
・治療期間が数ヶ月から半年以上と長期間に渡る
・ほとんどの場合保険が適用されず、費用が高額
義歯
<メリット>
・短期間で治療できる
・周りの歯をあまり削らなくて済む
<デメリット>
・クラスプが目立つ
・鉤歯に負担がかかる
・硬いものが食べにくいことがある
・外れることがある
・手入れが面倒
6、患者説明用のトークスクリプト
 患者さんに対して、ブリッジ、インプラント、義歯のどれを選択するか確認していくためには、前述のメリットデメリットをお伝えした上で審美面・健康面・機能面に分けて提案してみると患者さんの気持ちを引き出しやすいかと思います。
患者さんに対して、ブリッジ、インプラント、義歯のどれを選択するか確認していくためには、前述のメリットデメリットをお伝えした上で審美面・健康面・機能面に分けて提案してみると患者さんの気持ちを引き出しやすいかと思います。
患者さん自身が審美面・健康面・機能面のどれを重要視するかをまず確認します。
審美面であればお口の見た目を気にされるということですから、鉤がなく歯に近い色を作ることができるブリッジもしくはインプラントとなります。
健康面であればご自身の歯を削ることのない入れ歯か、手術を受けても良いのであればインプラントとなります。
機能面を重視される方は硬いものも食べることが出来るインプラントか、自然な咀嚼感を得られるブリッジに軍配が上がります。
8、まとめ
このように、まずは患者さんが審美面・健康面・機能面のどれを重視するのかをまず確認し、その上でそれぞれのメリットデメリットについて確認していけば、患者さんもセットした後のことを想像しやすくなり、選択することも容易になります。
ただそれぞれの補綴物について話すだけでなく、患者さんの目指す口腔内を聞きだしながら一緒に考えてみてくださいね。
歯科衛生ライター:moe
※1 厚生労働省(平成28年)より引用 https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/dl/62-28-02.pdf
※2 ブリッジの考え方2007より引用 https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/hokkaido/shinsei/shido_kansa/bridge/000214986.pdf
※3 公益社団法人日本補綴歯科学会 保険導入された高強度コンポジットレジンブリッジ(高強度硬質レジンブリッジ)より引用 https://www.hotetsu.com/files/files_243.pdf
※4 歯の欠損の補綴歯科診療ガイドラインより引用 2008https://www.hotetsu.com/s/doc/guideline_2008.pdf
歯科医療の現場で役立つ実践的な知識を届けるORTC

ORTCは「笑顔の役に立つ」を理念に、歯科界の知識を共有する場を目指しています。歯科医療の現場で役立つ最新の知識と技術を提供することで、臨床と経営の両面からクリニックの成長を支援します。最先端の技術解説や経営戦略に特化した情報を集約し、歯科医療の現場での成果を最大化。自己成長を追求するためのコンテンツをぜひご活用ください。
無料会員登録
無料動画の視聴、有料動画のレンタルが可能です。歯科業界についてのオンライン・オフラインセミナーへの参加が可能となります。
ORTCPRIME
今なら77%OFFの月額 2970円で、 ORTC内のすべての動画を見放題に。臨床の現場に役立つ最新の技術解説や、歯科医院経営の成功戦略を網羅した特別コンテンツをご利用いただけます。 歯科業界の方へ効率的に知識を深めていただける内容です。
ORTC動画一覧
ORTCセミナー一覧
まずは無料会員登録
こちらのリンクより会員登録ページへお進みください。
会員登録はこちら
ORTCPRIMEへのアップグレードも簡単!
登録後は「マイページ」から、ORTCPRIMEにいつでもアップグレード可能です。
 こちらの動画もおすすめです
こちらの動画もおすすめです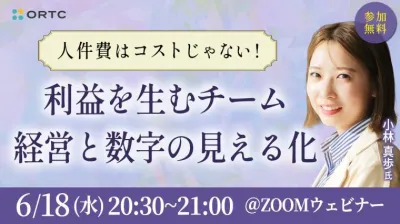 「人件費はコストじゃない!利益を生むチーム経営と数字の見える化」
「人件費はコストじゃない!利益を生むチーム経営と数字の見える化」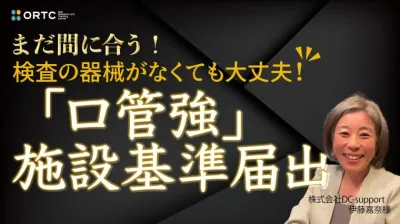 【大好評につき再配信】検査の器械がなくても大丈夫‼︎ 「口管強」施設基準届出
【大好評につき再配信】検査の器械がなくても大丈夫‼︎ 「口管強」施設基準届出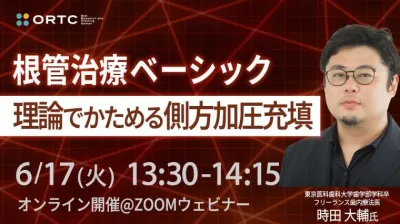 根管治療ベーシック 理論でかためる側方加圧充填
根管治療ベーシック 理論でかためる側方加圧充填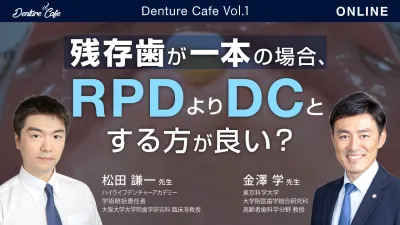 残存歯が一本の場合、RPDよりDCとする方が良い?|Denture Cafe vol.1
残存歯が一本の場合、RPDよりDCとする方が良い?|Denture Cafe vol.1 キャッシュを生む医院経営×投資の黄金律:ポスト・ バフェット時代に備える資産戦略
キャッシュを生む医院経営×投資の黄金律:ポスト・ バフェット時代に備える資産戦略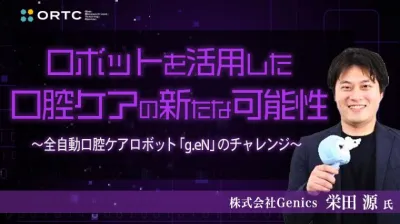 ロボットを活用した口腔ケアの新たな可能性 ~全自動口腔ケアロボット「g.eN」のチャレンジ~
ロボットを活用した口腔ケアの新たな可能性 ~全自動口腔ケアロボット「g.eN」のチャレンジ~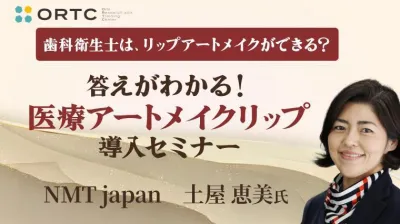 歯科衛生士は、リップアートメイクができる?答えがわかる医療アートメイクリップ導入セミナー
歯科衛生士は、リップアートメイクができる?答えがわかる医療アートメイクリップ導入セミナー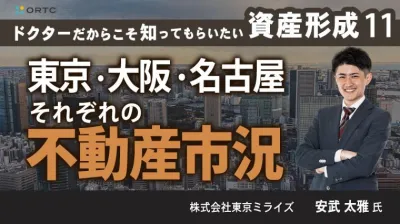 ドクターだからこそ知ってもらいたい 資産形成⑪ ~東京・大阪・名古屋それぞれの 不動産市況~
ドクターだからこそ知ってもらいたい 資産形成⑪ ~東京・大阪・名古屋それぞれの 不動産市況~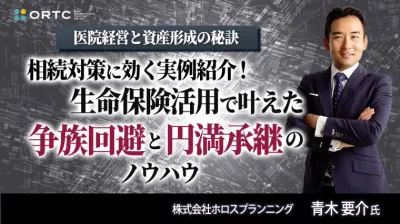 医院経営と資産形成の秘訣 ー相続対策に効く実例紹介!生命保険活用で叶えた“争族回避”と“円満承継”のノウハウー
医院経営と資産形成の秘訣 ー相続対策に効く実例紹介!生命保険活用で叶えた“争族回避”と“円満承継”のノウハウー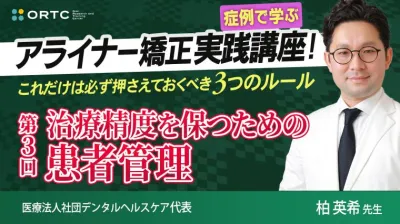 【症例で学ぶ】アライナー矯正実践講座! これだけは必ず押さえておくべき3つのルール 第3回 治療精度を保つための患者管理
【症例で学ぶ】アライナー矯正実践講座! これだけは必ず押さえておくべき3つのルール 第3回 治療精度を保つための患者管理

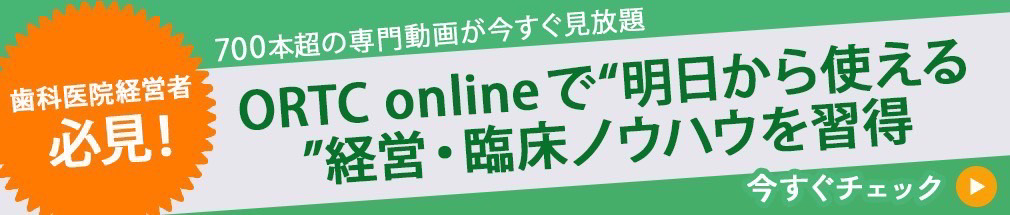

 支台歯形成とは、補綴物を被せる際の土台となる歯の形態を形成することです。
支台歯形成とは、補綴物を被せる際の土台となる歯の形態を形成することです。
 患者さんに対して、ブリッジ、インプラント、義歯のどれを選択するか確認していくためには、前述のメリットデメリットをお伝えした上で審美面・健康面・機能面に分けて提案してみると患者さんの気持ちを引き出しやすいかと思います。
患者さんに対して、ブリッジ、インプラント、義歯のどれを選択するか確認していくためには、前述のメリットデメリットをお伝えした上で審美面・健康面・機能面に分けて提案してみると患者さんの気持ちを引き出しやすいかと思います。